ストラヴィーンスキィと富士の裾野のストラヴィーンスキィ
2017夏コミックマーケット92へ出品したオリエント工房主催同人誌「伊福部ファン」0号へ寄稿したものを少し修正 「ハモンドオルガン」 → 「コンボオルガン」 したものを全文掲載します。ウェブで読みやすいよう、改行は1行空けにしてあります。
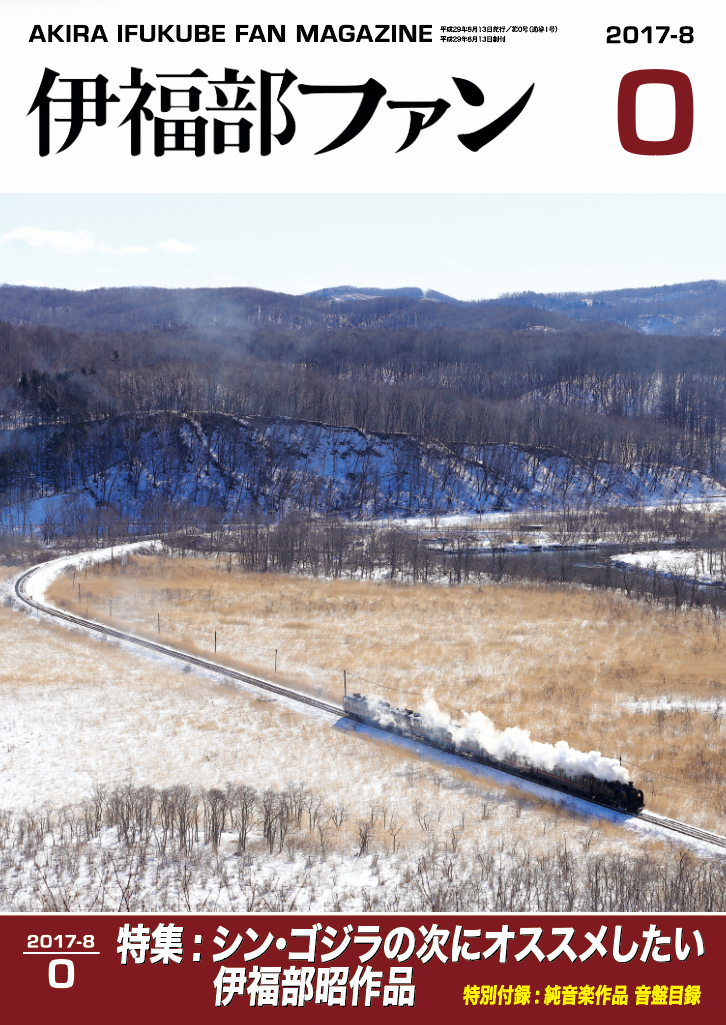
ストラヴィーンスキィと富士の裾野のストラヴィーンスキィ
2017夏コミックマーケット92へ出品したオリエント工房主催同人誌「伊福部ファン」0号へ寄稿したものを少し修正 「ハモンドオルガン」 → 「コンボオルガン」 したものを全文掲載します。ウェブで読みやすいよう、改行は1行空けにしてあります。
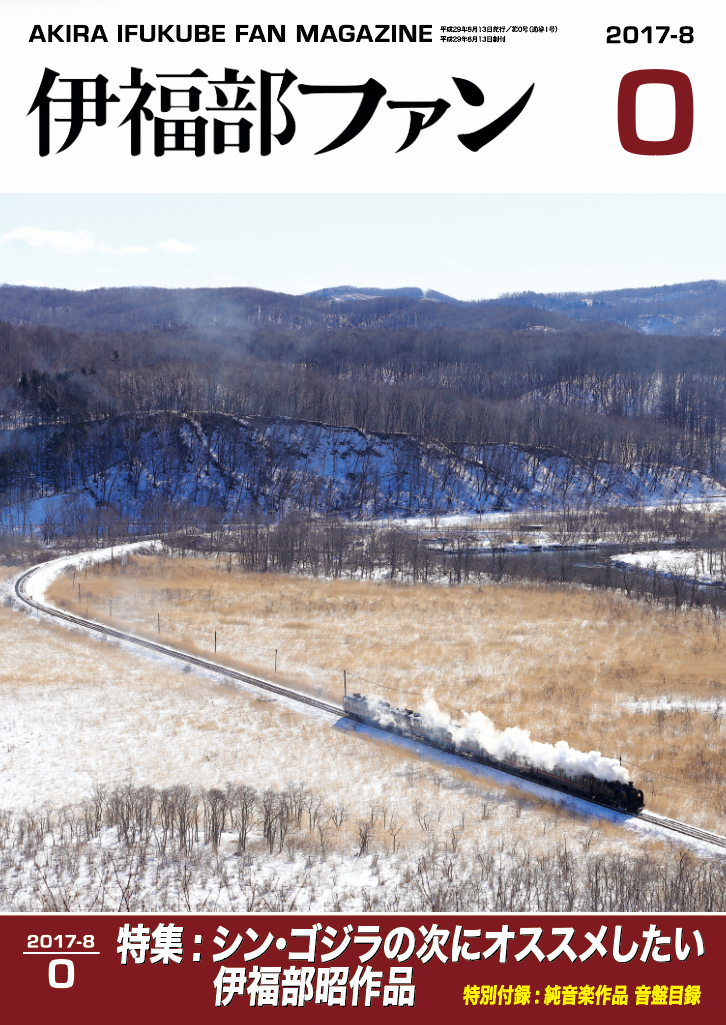
はじめに
私の古い個人サイト「後の祭」の中に伊福部昭のページがあり、この寄稿はその延長上の単なる読み物となる。けして研究発表や論文ではない。特段、特筆するようなことは書かれないと思うが、私が二十年以上伊福部を聴きながら感じていること、感じてきたことのうち、最新の想いをこの機会に連ねてみたい。
とりとめもないものの羅列になると思われるが、長文のツイートと思って、ご容赦いただきたい。
1.フランス音楽的なもの
私は伊福部聴きとしては意外に感じられるかもしれないが、特撮に関しては全く素人以下でゴジラもまともに観たことが無かった。今でもシリーズ全体の半分も観ていない。世代的にメカゴジラの逆襲が1歳であって、とうぜん観ていない。
それからずっとゴジラは無くてゴジラ(1984年)で6年生、ゴジラVSビオランテで高2、そこそこ面白かったが、それほどハマるというものではなかった。
ようやくスクリーンでたっぷりと伊福部を聴いたのはゴジラVSキングギドラで、もう大学生だった。そもそもあまり思い入れが無いし、映画自体はまったくぴんと来なかった。キングギドラはかっこよかったけれども。
それでも、そのころ矢代秋雄や武満徹、芥川也寸志を聴き出していたので、あくまでその延長で「純粋に日本人作曲家の一人」としての伊福部昭に興味が出て、喜寿記念の二枚組み「伊福部昭の世界」(TYCY5217/18
)と芥川也寸志/新交響楽団の演奏「伊福部昭 管弦楽選集」(FOCD3245)のCDを買って、ようやく伊福部へ本格的にハマった。従って、私にとっての初伊福部は交響ファンタジー「ゴジラVSキングギドラ」、タプカーラ交響曲、日本の太鼓「ジャコモコ・ジャンコ」、交響譚詩、ヴァイオリン協奏曲第2番だった。
特撮等のサントラの復刻も含めて、この90年代初頭が伊福部の「CDによる復興」の先駆けだったように思える。
当時はウィンドウズも無かったし、ネットはネット通信の時代で伊福部関連の書籍もほとんど無く、これらのCDのブックレートがたいへん貴重な情報源だった。そこに書かれてあることで、私も杓子定規に伊福部昭は日本を代表する民族楽派、という蒙にとらわれていった。
もちろんそれは間違いではない。本州各地より北海道へ伝わった各種の民謡を題材にしたピアノ組曲やそれを管絃楽化した日本組曲あるいは日本狂詩曲などの作品、アイヌ伝承に想を得てアイヌ音楽の素材を使用した土俗的三連画や同じくアイヌ等を題材とした初期の歌曲集など、これらは楽想的にも日本民族楽派と云ってまったく問題ないテイストを備えている。
が、パッと聴いてそれと分かるのは「それしか」無い。初期の作品はたしかに音階や旋律的にもその傾向にあるが、晩年まで含めると全体的な作風や書法が土俗的だからというだけで、伊福部を純粋な日本民族派とするのはちょっと乱暴な定義なのではないかという疑問が聴いているうちにわきあがってきた。むしろ、それをいうなら日本北方楽派ではないのか。大木正夫が、同じくまったく異なったテイストによる日本狂詩曲を書いて伊福部の「日本」を否定というでも無いが暗にあれはちょいと違うよ、としているのも興味深い。また北方だって日本じゃないかと云われると、それもそうである。
そんなことを思いながら日本狂詩曲そして特に土俗的三連画を繰り返し聴いているうちに、さらにふと思ったのが、ずいぶんこの初期の曲の書法がフランス音楽に似ているなあ、ということだった。
スコア研究に長け、大著「管絃楽法」を上程した伊福部のことだから、研究の結果、技術的にフランス音楽に影響があるといえばあるのだろう。しかし、フランスの和声や書法を日本の旋律や素材に合体させてどうたら……というものではない。
ここで云うのは、若き伊福部のフランス音楽への憧れのようなものがあるのではないか、ということである。
さて、しかしフランス音楽の専門的な愛好家ならいざしらず、普通のクラシックファンにとってフランス音楽というのはすなわち印象派で、ドビュッシーとラヴェルというのは想像に難くない。ドビュッシーやラヴェルを経て「六人組」のうちの誰かを好きになった人は、もう一般的にはフランス音楽のマニアな道に入っていると云ってよいだろう。
そして、ここでいうフランス音楽とは、云うまでもなくその六人組である。
ちなみにフランス六人組とは、デュレ、オネゲル、ミヨー、タイユフェール、プーランク、オーリックとなる。
ドビュッシーやラヴェルも当たり前として聴いていただろうが、まず学生時代の伊福部は熱心なサティ信者であった。そしてストラヴィーンスキィ、ミヨー、ファリャなど、当時としては異様なほどマニアックな「現代音楽」の作曲家を愛好していた。数え上げればきりがないが、チェレプニン賞において日本狂詩曲を評価した審査員の面々もまた、フランス人作曲家だった。
当初、審査員にラヴェルの名があり、伊福部はラヴェルに曲を見てもらいたいと頑張ってスコアを仕上げて応募したが、ラヴェルはこのころ脳神経系の病が悪化して審査員を辞している。
そこでルーセルが中心となり、タンスマン、ジル=マルシェ、ブリュニエール、イベール、ハルシャニー、フェルーが伊福部らを審査した。今ではルーセルとタンスマン、イベールくらいしか高名ではないかもしれないが、当時はパリ楽壇のお歴々といったメンバーだ。
伊福部ファンにとってはこのようなことは常識の範囲内であると思うのでこの辺にしておくが、伊福部にとって憧れのお歴々に認められた嬉しさというのは、ちょっと我々には理解しえない想像を絶するものがあったのではないかと推察される。
なんといっても日本狂詩曲に次ぐ作品である土俗的三連画の正式な海外語のタイトルはフランス語で Triptyque
Aborigne である。
では、具体的に初期作品のどのような部分がフランス音楽的なのか……に移るが、本来であれば譜例を示してここがこう、ここがこう、とするのがよいのだろうが、それでは音楽論文だ。私はそういうのはできないし、する気もない。そういうのはもっと音楽学の専門的な方々におまかせして、ここではあくまで文藝的な表現でそれを探ってみたい。
まずピアノ組曲は確かに民族的な音形や音調をとっているが、そのモダンで複雑な書法は例えばイッポリートフ=イヴァーノフの組曲「コーカサスの風景」のような単純な民族的旋律によるエキゾチック組曲というより、プーランクやミヨーのフランス組曲又はイベールの交響組曲「パリ」に匹敵する。ただし作曲年はイベールの交響組曲「パリ」が1931年、プーランクのフランス組曲が1933年、ミヨーのフランス組曲は1945年と、伊福部のピアノ組曲の1933年と比べると同年代かずっと後年である。それは直接参照にしたとかではなく、それらに匹敵する位置づけであるという意味。
ピアノ組曲は単なる民族音楽をクラシック風に編曲したものではなく、民族音楽を素材とした純粋な創作組曲であり、そのモダンな構成や響きは単なる民藝クラシックを超えたエスプリがあって、それがフランス音楽的だと考えている。
日本狂詩曲は、その肥大し、ティンパニが音を変えられることを知らなかったために転調してもティンパニだけはずっと同じ音……のような素人臭の残る反面、指揮者の高関健をして「何の楽器がどう鳴るのかを全て把握してある。こちらは何も考えずに振れば鳴るようになっている」(BSプレミアム「クラシック倶楽部 日本人作曲家名作選 伊福部昭」平成26年5月30日放送より)という天才的で独特のオーケストレーションが明らかにストラヴィーンスキィの春の祭典に影響されていることからも、これをフランス的、あるいはフランス的というには云いすぎだとするならばフランスっぽい、と云ってよいと思う。
さて、どうして春の祭典がフランス的なのか? ロシア音楽ではないのか? と思われるのは当然だ。
しかしそれは、単にロシアの原始的な風景(古い神話を含む)素材を用いロシア民謡から素材を得ているだけで、それでロシア音楽と断ずるのは、私には違和感がある。なにより、このバレエが演じられたのはパリであるし、フランスで生まれた音楽だから。
したがってフランス音楽である、とまでは云わない。ストラヴィーンスキィはフランス人ではない。ただ、フランスのエッセンスの中でロシアを題材として生まれた音楽、であるとは云えると思う。
そんなフランスのエッセンスの詰まったロシアを題材としたリズム重視の大管絃楽曲と、フランスのエッセンスの詰まった日本を題材としたリズム重視の大管絃楽曲が、コンセプト的に似るのは当たり前だ。なにより伊福部はこの春の祭典のレコードを聴き、それまで日本において主流であったドイツ音楽ではなく、「こういうのも《音楽》なのか」と感嘆し、それなら自分も作曲ができると思ったというのだから、初めてのオーケストラ曲がハルサイめくのは、これも自然なことだろう。
次が土俗的三連画だ。この小編成のモダンで色彩的に小洒落た曲は、間違いなくフランス音楽の影響にある。むしろ類似性を探ってゆけば、こういう音楽を作るのはフランス人かその影響化にある作曲家しかいない。まず編成が日本狂詩曲の反動で一管編制なわけだが、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン2 、トランペット、ティンパニ、ピアノ、ヴァイオリン2 、ヴィオラ、チェロ、コントラバスと、これは伝統的な編制である。しかしそこから生じる音楽は実に自由闊達で、ソナタ形式とか三部形式とか、そういうものからは解き放たれている。フランス音楽とはいえプーランクやミヨーなどの新古典的な作曲技術と比べると、そちらの方がソナタ形式などにこだわっている。もっと自由な形式という観点では、伊福部はラヴェルに近いと考える。
交響譚詩はどうだろう。これは次節にも関係あるが、私が伊福部は純粋な民族楽派というのに違和感を感じたのは、まさにこの交響譚詩からだった。つまり、最初に聴いたCDから感じていたことになる。これはどう聴いても民族派の曲ではない。むしろドヴォジャークに近く、国民楽派ぐらいだろう。
民族楽派と国民楽派はなにが違うのかと云われると、私もクドイ国民楽派が民族楽派というほどの認識しかないが、交響譚詩はどの演奏を聴いてもサッパリ、アッサリしている。そのアッサリさが、最初のころは私も「伊福部は民族楽派だ」という蒙により、聴けば聴くほど「伊福部にしては堅苦しい曲」と思っていた。
これは、プーランクの新古典的な交響曲あたりに非常に雰囲気が似ている。キングレコードの伊福部昭作品集の作者本人の解説によると、実際これをシンフォニーと銘打ってもよかったがそうしなかった、とある。また、第2楽章のフルートソロは日本の祭り囃子の笛を模している、ともある。その意味で民族派、あるいは書法の点で国民楽派と云っても良いが、やはり聴いてみるともっと新古典派の曲と断言できる。第1楽章はソナタ形式を模している。伊福部最晩年の弟子の話を聞くに、伊福部は意外と形式にこだわっていて交響曲の第1楽章はソナタ形式ではなくてはならない、とゼミナールで語っていたという。
とはいえ、伊福部の云う通り供養、追悼の意味もあって仄かに暗く日本的に湿っており、アポロ的な解放感は無いかもしれない。特に第2楽章である第2譚詩は完全に和風レクイエムだ。
音詩「寒帯林」は交響詩なのに音詩としている部分がまずシベリウス的ではあるが、多楽章制というのも珍しい。その意味で、これは交響曲的といえる。それもフランス式の3楽章制交響曲だ。が、音楽としては特段フランスの味はない。外観だけがフランス式の3楽章制交響曲に似ている、というだけのものだろう。
となるとタプカーラ交響曲は、完全にフランス式外観を備えているといえる。これに関しては、たんなる偶然といえばその通りなのだが、共通点として挙げてもおかしくない偶然と云える。
そもそも交響曲はフランスにおいて急緩急の三部形式の序曲「シンフォニア」が拡大・発達したもので、3楽章形式だった。それがドイツへ渡って、ピアノのためのソナタやヴァイオリンのためのソナタと同列の「オーケストラのためのソナタ」という意味で4楽章制になった。古い形式の3楽章製の短い交響曲もあるにはあるが、変わり種といえる。
それがフランスへ逆輸入され、フランスでも交響曲は4楽章制が主流となっていた。
ところが、フランクが第2楽章にスケルツォに相当する部分と緩徐楽章を混ぜこんで、古い形式の3楽章制を新たな概念で復興させてから、フランク伝統のフランス交響曲はたいてい3楽章制になっている。ただ、ルーセルやミヨーなど、4楽章の交響曲もある。
ちなみに、ベルリオーズだけはフランスの作曲家という枠を超えて唯一無二の存在となっているので例外。
さてタプカーラ交響曲は3楽章制で、その意味でフランス式の外観をもっている。その代わり、純粋なフランク様式ではない。スケルツォに相当する部分を完全に欠いているためだ。純粋なフランク流ならば第2楽章に速い部分が無くてはならないし、循環形式が求められる。だからタプカーラ交響曲とフランスの交響曲を比べてもただ単に3楽章制なだけという共通点しかないのだが、そうはいっても3楽章形式だ。プーランクやミヨーの新古典的な交響曲とフランク流の伝統とが合体したような、独自の交響曲の姿をもっている。またその音楽の進み方は、片山杜秀をして序破急形式と云っている。そのフランク様式と新古典的な様式に日本的な様式の合体は、土俗的でありながら格調の高さを与えている。ただ単にエキゾチックな鳴り物交響曲ではない。
ピアノ組曲を管絃楽化した日本組曲にあっては、その素材に対する扱いはピアノ組曲に共通するので割愛する。ここで題材に上がるのは当然オーケストレーションとなる。伊福部のオーケストレーションのうまさは私ごときが述べるまでもないが、その妙味を味わえる絶好の素材がこの日本組曲だろう。というのも、他にもリトミカ・オスティナータ、プロメテの火、日本狂詩曲など、ピアノリダクションの曲はある。が、それはあくまでリダクションであって、オーケストラ→ピアノという作業となる。当曲にあってはピアノ→オーケストラという、その通りオーケストレーションを比較して楽しめる。しかも、17〜19歳にかけて作曲したデビュー作に匹敵する最初期のものを、70を超えてオーケストラ化するというこの凄さ。3管編成の大オーケストラの鳴り響く様を原曲のピアノ曲と聴き比べられる面白さ。盆踊や佞武多の小節数も若干増えている。
それでフランス的という話題だが、伊福部のオーケストレーションの基礎はリームスキィ=コールサコフの教え子であるストラヴィーンスキィの影響、なにより「オーケストラの魔術師」ラヴェルの影響、そうなるとイベールやルーセルという瀟洒や色彩の取りこみ、オネゲルの重厚さ・構築性など……他に例えようのない、いかにもフランス的な妙味をもっていると思う。
オーケストラというのは、ドイツにおいて絃楽器が高価だったため絃楽合奏で楽器が足りず、音の不足した部分をドイツの民族楽器(ホルンとオーボエ)で補ったのが原型で、その際に管楽器は2本ずつだったので2管編成が基本となった経緯がある。
つまりオーケストレーションの基本中の基本は絃楽化がまず根本で、そこに管楽器が補助で入って、打楽器が最後にアクセントとして入れられる。具体的には「メインの旋律は絃でやるのが基本」となる。
それが、19世紀になって絃楽器と管楽器の価値が同等となり、管楽器もバリバリメイン旋律を演奏するようになった。その理論を確立した最初期の人がリームスキィ=コールサコフということになる。マーラーやリヒャルト・シュトラウス、ラヴェルなどの煌めくようなオーケストラ効果は、絃と管と打の役割の価値が 絃>管>打 ではなく、絃=管=打 となったことが革命なのだ。
それを日本で最初にやったというか「やらかした」1人が伊福部というわけだ。それはやはり発想が異なる。ドイツ・アカデミズムを習った人は、当時はリヒャルト・シュトラウスやマーラーですら異端で、管楽器やまして打楽器が絃楽器を押しのけて鳴り響くなどというオーケストラは「ド素人」「何もわかってない」のたぐいであり、日本狂詩曲などはただでさえ恥ずかしげも無く日本的旋律を使っているうえにオーケストレーションは滅茶苦茶で、春の祭典という「ゲンダイオンガク」の悪しきエピゴーネンであり、国辱だから審査へ送付するなとまで云われた。それをとりなしたのが大木正夫であり、大木は後年、伊福部へ「おれのおかげでお前は賞をとれたんだぞ」と笑いながら恩を売ったというのは余談。
ところが伊福部にしてみれば、最初から日本狂詩曲は「もともと打楽器合奏を伴奏としたヴァイオリン協奏曲」という、21世紀でも斬新な発想なのだから恐れ入る。
話がずれたが日本組曲はフランス的なエッセンスが入ったものに老練の熟達が加わった、伊福部オ−ケストレーションの完成形を味わえる逸物であると断言したい。
なお、この後のオーケストラ作品は交響的音画「釧路湿原」と交響組曲「わんぱく王子の大蛇退治」だが、前者は映像作品の付随音楽、後者は映画音楽の編作であることを考えると日本組曲こそが制約のない自由なオーケストレーションの完成にして究極であると付け加えたい。
また、伊福部が19歳で作曲したピアノ組曲を57年後に管絃楽化した際に、ラヴェルが20歳で作曲した古風なメヌエットを35年後に管絃楽化した実例が頭にあったのかもしれない。
さて、こんな感じではあるが伊福部の中に潜むフランス的なものの片鱗を感じていただけると嬉しい。伊福部はフランス音楽の影響下にあるとか、日本を代表するフランス楽派であるとか、そういうものではない。あくまで、個人的に伊福部に感じているフランス的なものをご紹介しただけだ。そこはご理解いただきたい。
総体として伊福部昭とはドビュッシーのスケール感、ラヴェルのニヒルさ、サティの孤高、オネゲルの構築性、イベールの豪奢、プーランクの洒脱、ルーセルの色彩、ストラヴィーンスキィのリズム狂に北海道をドーン! した音楽的存在であると、とらえている。
閑話休題1 〜バッカナール好きなフランス作曲家〜
ローマ神話のバッカスは酒の神として高名だ。ここでいう酒とはもちろん葡萄酒……ワインであって、ビールやウヰスキーではない模様。このバッカスは、ローマ神話の元となったギリシャ神話ではデュオニソスとなる。
このバッカスを讃える飲めや歌えの古代の祭りがバッカナールだ。また、それをしてバッカス祭ではなく単なる狂乱じみた無礼講の饗宴という意味で、バッカナールと題されることもある。が、正確にはバッカナールはバッカス祭、あるいはバッカスの祭りというのが正しい日本語訳で、単なる「饗宴」は意訳と云ってよいと思う。また、せめてバッカスではなくとも「酒神祭」くらいになると、その土地の神においてのバッカナールという意味は持つことができる。
これは異国情緒にあふれた題材として、西洋のバレエやオペラなどにちょくちょく登場する。が、単に饗宴というと淫靡なイメージも少なからずつきまとうが、バッカナールというと、とにかく陽気なお祭り騒ぎ、という意味が強いと私は感じている。
聴いたことも無い無名なものも含めればそんなことはないのだろうが、高名な作曲家で少なくともCDになって自由に聴くことができるレベルでこのバッカナールという題材で音楽を書いているのは、ほとんどフランスの作曲家なのだ。
これは偶然でもあるのだろうが、フランス人のワイン好きがそのような題材をやはり好んでいると考えると、とても楽しい話題ではあるだろう。
まずドリーブのバレエ音楽「シルヴィア」よりバッカスの行進を。バレエ自体がローマ神話を題材としており、第三幕で主役たちがバッカナールの行われている神殿へ行く。パンパカパーン、パンパカパーンと明るいファンファーレよりはじまり、みなが陽気に歩いて行く様子が目に浮かぶ。5分ほどの曲で、吹奏楽編曲でも高名な一曲。
次は、サン=サーンスのオペラ「サムソンとデリラ」よりバッカナールを。こちらは旧約聖書によるオペラなので、題材的には異教徒の饗宴という意味でのバッカナールとなる。8分ほどの曲で、さすがサン=サーンス、見事なまでの異国情緒と乱痴気騒ぎ、加えて書法の確かさで職人の仕事だ。オーボエやホルンが朗々と奏でる異国旋律に打楽器がノリノリで場を盛り上げる。これも吹奏楽編曲で人気がある。
イベールにもバッカナールがある。これはBBCの委嘱による純粋なオーケストラピースだが、イベールはどうしてしまったのか、というほどにド派手で豪快でイケイケでアッパラパーな音楽だ。が、その豪放磊落さの中にもイベールらしい洒脱や軽妙が潜んでいるたいへんに魅力的な1曲。これも8分ほどだが、冒頭だけでも結婚式の新郎新婦の入退場に使用すれば盛り上がると思っている。
最後がフローラン・シュミットという作曲家が吹奏楽(軍楽隊バンド)のために書いているデュオニソスの祭りという曲。これはもちろんバッカナールのこと。10分少々の曲で、吹奏楽オリジナル曲としては古典だが内容は現代的なもので、分かりやすい旋律が気持ちよく流れるものではない。演奏難度も高くクラシック音楽界ではマニア的な存在だが、この曲のおかげでフローラン・シュミットは吹奏楽界では一定の知名度がある。なお、ドイツの作曲家にフランツ・シュミットという人がいて、どちらもイニシャルまで同じなので、ここではフルネームで書く。フローランはドイツ系フランス人。
ここらが高名作曲家の手によるCDにも YouTube にもある高名曲としてのバッカナールだが、みなフランス人作曲家なのは、面白い偶然だと思う。
フランス以外ではかのヴァーグナーが歌劇「タンホイザー」にバッカナールを書いている。これは愛好家以外はあまり知られていないと思うが、タンホイザーのパリ公演に際して当時のパリでは「オペラの幕間にバレエが上演されるという慣習」があり、ヴァーグナーは興行主よりバレエのための曲を書き加えるよう依頼された。
しかしヴァーグナー、そんな慣習なんぞ知るかボケと断固拒否。それで大騒動になり、新聞で醜聞として突き上げられ、ついに折れてタンホイザーにバレエを1曲加えることになった。それがバッカナールと題される一場である。
ヴァーグナーのオーケストラ作品集では、たまにタンホイザー序曲に続いてこれもまた10分少々のヴェーヌスベルクの音楽というものがひっついている場合がある。このヴェーヌスベルクの音楽が、書き加えられた(正確には改訂された)バッカナールだ。これは経緯がややこしくて、初演であるドレスデン版のヴェーヌスベルクの音楽を改訂してバレエ音楽のバッカナールとしたのがパリ版で、それをさらに改訂したヴィーン版もある。パリ版を演奏したCDにはよく序曲と一緒に収録されているが、なぜか大抵のCDではバッカナールではなくドレスデン版のタイトルのヴェーヌスベルクの音楽のままになっている。
カスタネットがカタカタ鳴ってヴァーグナーにしては面白い音楽だが、相変わらずの壮大な調子であり、あまり飲めや歌えのお祭り騒ぎというイメージは無い。歌劇は苦手なのでタンホイザーも観たことが無く、どのようなバレエのシーンなのかは知らない。
伊福部にもバッカナールがある。音詩「寒帯林」の第3楽章「山神酒祭樂」だ。これはバッカス神ではないが、山神の祭典という意味で伊福部のバッカナールといってもよいだろう。8分ほどで、満州楽を素材としており、素朴で土俗的な踊りの音楽を楽しめる。ゴジラ音形の元も出てくる。ゴジラ音形としては、現在知られている中ではおそらく最古のものだろう。
また伊福部の弟子の黛敏郎には、逆に饗宴という名の10分ほどのオーケストラ曲がある。豪快でジャズテイストもある実験的な楽しい曲だが、これの英語タイトルがバッカナールとなっている。1954年の作曲当時、世界でもオーケストラへこれほど大胆にジャズテイストを入れこむのは珍しい試みで、かなりモダンなバッカナールといえるだろう。かのバーンスタインがこの曲を聴き、1957年のウェストサイド・ストーリーの参考にしたのではないか? というほどだ。
バッカナールだけで、ひとつの演奏会の企画ができそうなほど、意外と面白い素材だと思う。そういう演奏会があったら、休憩時間に飲みすぎないようにしたい。
2.日本の伝統を背負った古典主義
伊福部の中にフランス的なものを感じつつ、それでもなお私は、伊福部は日本民族楽派の筆頭であると思いこんでいたわけだが、それはやっぱり間違いではない。見方(聴き方)によれば、確かにそれは正しい。伊福部が民族楽派でなければ、他に誰が日本民族楽派となるのだろうか。
だが、その観点から云うと交響譚詩などは土俗的ではあるがなんにも民族っぽく無く感じ、伊福部の中ではちょっと変わった位置づけの曲なのかな、という違和感をずっと引きずっていた。
タプカーラ交響曲もそうだった。実際この交響曲は特定のアイヌ音楽の旋律など何も使っていない。3楽章のアクセントのとり方や、理念として名前だけ頂いている形なので、伊福部のあらゆる魅力の集大成ではあるが私にとっては民族的でもなんでもない。単純にタイトルや作曲理念、または一部アクセントのとり方だけでこれを民族楽派というのであれば、私とは民族楽派の概念が異なる。
6曲ある協奏曲も、日本的旋律を使っているわけでも無く、特段、具体的にこれという民謡などを使っているわけでも無い。ただし交響的エグログは日本の伝統楽器の協奏曲だし、リトミカ・オスティナータは日本音階に近い6音階を使っている。
それだけをもってそれらも民族楽的な曲とは云えないし云いたくない。
それで、伊福部は一部初期の曲において日本民族楽派ではあるだろうが、もっとグローバルに満州や樺太を含めた日本北方楽派なのではないか、という認識に移った。そうなるとギリヤーク族の古き吟誦歌やサハリン島先住民の三つの揺籃歌、寒帯林なども包括できると考えた。
それが根底から覆り、その違和感が確信に変わったのが2014年に発売された「伊福部昭 古稀記念交響コンサート 1984」(NOOI-5011〜13)だった。この3枚組CDの3枚目において、1984年に行われた伊福部昭古稀記念コンサートの打ち合わせを兼ねた古弟子たちとの食事会の録音の一部が公開されたものである。
ここで伊福部は自分で、驚天動地な発言をしている。つまり、自分は作風として古典主義を目指している、と。
「は?」
一瞬、我が耳を疑った。
だが、いわゆる古典派のハイドンとかモーツァルトとか初期のベートーヴェンとかの作品とは響きや書法がぜんぜんちがう。伊福部も「そういうのとは、ぜんぜんちがいますよ。ええ、ちがいます」と断言している。しかし、目指すところは「日本の伝統を背負った古典主義」なのだという。
これには私だけではなく、周囲の芥川也寸志、松村禎三、池野成、石井真木らも「へぇーえ……?」「え……どこが……?」というようなしょっぱい反応。まさかこの歳になって、何十年もつきあった師の口からそのような言葉が出てこようとは? という、戸惑いすら感じさせる空気感が録音の奥から伝わってきて、とてもリアルだった。
伊福部はここで、ドビュッシーですら自身では印象派と呼ばれるのを嫌い、牧神の午後への前奏曲もあえて云うなら新古典主義であると云いきっている。
これにはまいった。
眼から鱗が五万枚、幽体離脱級の驚きと衝撃だった。
が、なにも作者がそう云ったからとて、それへ阿諛通従する必要はない。作者がどう云おうと「伊福部は日本民族楽派ったら民族楽派!」と思うのも、何も問題ない。
私の場合は、伊福部は日本民族楽派と思いそう主張しつつもどこかでずっと疑問を感じていた。本当にそうなんだろうか? と。交響譚詩や土俗的三連画は単なる民族楽派とはちょっと違うのではないか? と。
そこへ、伊福部自身が「おれは新古典主義だ」である。
まさか新古典主義と伊福部が自らの中で結びつくはずもなく、この発言は本当に面食らった。
と、ここで伊福部からちょっと離れるが、伊福部のその言葉でもっと長年のモヤモヤが晴れた作曲家がいる。大阪出身の大栗裕である。
大栗裕はナクソスの作品集でオーケストラ曲集も出ているが、大抵の認識は吹奏楽とマンドリンオーケストラの作曲家だろう。そのほか、オペラ、室内楽、現代邦楽なども多数書いている。
私は高校時代のブラスバンド部で吹奏楽のための神話を演奏して以来の熱心な大栗信者であるが、その初期作品のひとつ大阪俗謡による幻想曲ただ1曲をして、大栗を関西、あるいは西日本を代表する民族楽派と思いこんでいた。東の横綱を伊福部とすると、西の横綱は大栗だと。ごく初期の出世作ただ1曲のみでそう思いこんでいた。
さて、これも大栗ファンには常識なのであまり多くは述べないが、盟友の朝比奈隆がベルリンフィルへ客演した際に大阪俗謡による幻想曲の原典版を初演し、大栗はベルリンの批評家に「東洋のバルトーク」と呼ばれ、出世作となった。
確かにかっこいいあだ名だが、私はこれがたいそう意味不明で……大栗のどこがバルトークなんだろう、とずっと思っていた。なぜなら私は大栗を民族楽派と思っていたし、バルトークは民族楽派ではないから。バルトークと大栗の共通性は、民謡を素材としているだけだった。しかしバルトークはコダーイと異なり、民謡をバラバラにして組み立て直し、シュルレアリスムみたいな曲を書いているので、これは断じて民族楽派ではないと考えている。
どうして、ドイツの批評家は大栗をバルトークなんかに例えたのだろう? ずっと不思議だった。ドイツ人の耳には、そう聴こえたのだろうか。
また、私の大栗は民族楽派という認識とは対照的に、朝比奈の大栗演奏や大栗の自作自演の録音を聴くと、これがまことにザッハリヒな、緊張感はあるがえらいアッサリした、むしろ小気味よい粋を究めたような演奏で、これも違和感があった。テンポを引きずり、もっさりしたものは田舎臭くて逆に論外だが、もっとコテコテしてアゴーギクを強調した演奏のほうが大栗らしいのではないか?
しかも、大栗の好きな作曲家はモーツァルトとヨハン・シュトラウスだそうで、そういう音楽を目標として作曲していたのだという。
これなどは最も意味不明で、なにをどう聴いたら大栗の作風とモーツァルトやらヨハン・シュトラウスやらとつながるのか、ずっと考えていた。
そのときに、伊福部の「日本の伝統を背負った古典主義」発言。
いやあ、こんなところでつながった(笑)
大栗や伊福部にとって「日本的なもの」は、民族的な曲を作曲するための目標ではなく、日本人の作曲家として当たり前に利用する単なる素材(道具)であり、作曲技法や作曲する目標としては逆に古典的な、西洋音楽の伝統に則ったものだった。たまたまピアノ組曲や日本狂詩曲、大阪俗謡による幻想曲は、その結果として作曲の最初に民謡などを直接拝借したにすぎない。それは若さや未熟ゆえだったのかもしれない。
またそうなると、朝比奈や大栗の自作自演の聴こえ方が俄然ちがってくる。テンポだけ速くて素っ気ないと感じていたものが、厳しくもアポロ的な明るさすら持つ、つまり新古典的な、プロコーフィエフの第1番交響曲「古典的」にも通じる演奏法に聴こえてきた。
大栗こそそういう意味の発言は残っていないかもしれないが、その理想の作曲家、盟友や自作自演の表現法を鑑みるに、これこそ「日本(あるいは大阪、関西)の伝統を背負った古典主義」以外の何物にも聴こえないではないか。
そうなると、またこれがドイツの批評家の「東洋のバルトーク」発言が意味を成してくる。なぜならば、バルトークは少なくともその後期の作風……例えば管絃楽のための協奏曲や絃楽器と打楽器とチェレスタのための音楽、ピアノ協奏曲第3番などは、斬新ではあるが書法として完全に新古典主義あるいは新古典主義風だから。
もし、ベルリンの批評家が大栗の中へ日本の伝統を素材として利用し現代的に昇華した新古典主義的なものを感じて、それをバルトークに似ていると思ったのだとしたら……流石に、すごい耳をもっていると感心する。
そもそも大栗とてマンドリンオーケストラのためのシンフォニエッタや組曲のシリーズなどは、ことごとく3楽章制、ソナタ形式、三部形式、ロンド形式という明確な古典さである。フレージングや和声に日本的なものを素材としたバーバルさがあるだけで、その構造は完全に新古典主義だ。それが、どうして大栗はこんな曲を書くのだろうという意味で以前は全く納得ゆかなかったが、そう気付いてからは、これこそ大栗の本質と思うようになった。
またマンドリンオーケストラと朗読や歌唱のための音楽物語も、その構造としては平易で平明な歌劇を思わせるし、そもそも歌劇の作風もまったく古典的なもので、あまり前衛的な手法ではない。音源となっているのはこれも出世作赤い陣羽織のみだが、それはファリャの三角帽子を題材としたアレンジもので、作風はかなり古典的、かつ時代劇なので民族的だが、これは大阪俗謡のための幻想曲と同じ年の作曲であるため、初期の民族的例外作品といえるだろう。
だいたい、同じく民族的題材である夕鶴を作曲した團伊玖磨や具体的に民謡をパラフレーズした間宮芳生や柴田南雄がそれだけをもって民族楽派なのかというと、曲調も含めてまったくそんなことはないことをみても、1曲や2曲、直接的に民族的な素材や題材による曲があったとて、その作曲家が民族楽派であるとは限らないことが分かる。
伊福部へ戻る。
若いときの作品は、民族的な素材を「そのまま」使っていたが、それが若さゆえの技術不足あるいは考え方の未熟さであると位置づけると、それはむしろ例外である。伊福部の新古典的な、自身の一生の作風の目標を初めて掲げた真の創作のスタートは交響譚詩であると認識できる。
当初、私は伊福部の若いころの作品をもって伊福部を民族楽派として交響譚詩をイレギュラーな作品と考えていたが、それは逆だった。
むしろ交響譚詩から伊福部の純音楽の本質的な流れが生じる。一皮むけた、あるいは壁を超えた、というやつだ。戦後はたとえ民謡を使用していたとしてもあくまで題材や書法の一部として取り入れられるに停まり、民族的な旋律であろうとも伊福部の創作である。表現する作曲技術的には当然12音や無調でも無く、そうなると、国民楽派風、ロマン派風を含めても古典的としか云いようが無い作品が並ぶ。
ピアノ組曲を管絃楽化した日本組曲は、それはあくまで「オーケストレーション」がメインであって、曲の内容はピアノ組曲ほぼそのままなのだから例外といえる。
新古典主義というと、一般的にはヒンデミットの作品やプロコーフィエフの第1交響曲「古典的」、またストラヴィーンスキィの新古典時代の作品など、実際にバッハやハイドン、モーツァルト的な作品へ現代風の和声をつけたものやそれらを模したものなど、旋律や構造までもバッハやハイドンみたいな作品を思い浮かべるが、伊福部が云うのはあくまで「日本を背負った古典主義」であって、ハイドンなどの作風そのままでは無いのは既に述べてあるし、伊福部自身も述べている。そうではない。
そこに、日本的な題材や旋律や和声やリズムは、ちゃんと存在する。
だが、それは生ではない。加工されて、料理されている。生もいいが、手のこんだ料理もうまいものだ。その加工技術が、古典的伝統的なクラシックの技術というだけで、日本という素材は存在する。
加工されていても日本的な題材や旋律や和声やリズムが使われていれば、それは日本民族楽派だろうと云われれば、私とは民族楽派の定義が異なる。
伊福部を民族楽派というのはドビュッシーを印象派というに等しく、それは一般共通認識的に見ればなんら問題ないだろうが、本人にしてみれば「違いますよ」というもので、私は単純にその認識を作者と共有したいと考える。
閑話休題2 〜日本のバッカナール三景〜
日本を題材にしたバッカナールといえば、何をおいても、高天原のあの「事件」以外にない。つまり、天岩戸に天照大御神が引き籠もりもとい立て籠もり、世の中が真っ暗になってしまった事件だ。
その際、知恵の神である思金神の発案により岩戸の前で神々が飲めや歌えの大騒ぎ、天宇受賣命が踊ったのがまた「槽伏せて踏み轟こし、神懸かりして胸乳かきいで裳緒を陰に押し垂れき」というから、まるでトリップ系ストリップ。神がかって衣服も乱れ、胸やアソコが見えたさい、神々は(なぜか)ドッと大笑いして、自分がいなくなって真っ暗な世の中になったのに、どうしてみんなは楽しそうに笑っているんだろう? と思った天照、ちょっと岩戸を開けてドキドキしながらのぞいてみて、
「どうしてみんな楽しがってるの?」と、問えば、
「貴女様よりもっと高貴な神が現れたので、みなで喜んでおります」とのこと。
「ほんとうにそんな神がいるの? どこの神か?」と、問えば、
「この御方です」と、天照の前に差しだされたる御神鏡。
それへまぶしく映る神々しい神。それは自分の姿だが、さらに不思議に思った天照、もっとよく見ようと岩戸をさらに開けた。
そこを一気に天手力男神が岩戸を全開にして、天照を無事に世界へ連れ出す……というストーリーである。
その様子を音楽化したものを3曲紹介したい。その神々による飲めや歌え、酔っぱらって踊れ、の大騒ぎこそ日本のバッカナールというにふさわしい。
1曲目が、吹奏楽曲が原曲で、オーケストラ版もある大栗裕の神話だ。既に述べてあるが私は高校時代のブラスバンド部でこの曲のティンパニを叩いて以来、熱心な大栗信者である。
演奏時間にして14分ほどの当曲は標題性の高い交響詩的楽曲で、冒頭アンダンテのおどろおどろしい雰囲気は天照が隠れて暗黒になった世界を現す。そこへ、ミュートトランペットのけたたましい響きが常世長鳴鳥を現し、ついに10/8拍子で天宇受賣命の乱れに乱れる踊りが始まる。しかしどこか緊張感があるのは、楽しげな宴会の様子は作り笑いで、みな天照を無事に連れ出す作戦のために緊張しているのではないか、とすら思わせる。
踊りは4/4 拍子で行進曲調になって、そこから暗黒の世界がアンダンテの中間部として再現される。そして再び天宇受賣命の踊りがやや変奏されてはじまり、最後はドラの一打と共にコーダとなって、めでたく天照は高天原へ明かりを呼び戻すのだった。
オーケストラよりも断然吹奏楽で高名な曲なので、吹奏楽経験者はほとんどの方が知っているだろう。
2曲目が我等が伊福部昭の交響組曲「わんぱく王子の大蛇退治」よりその名もアメノウズメの舞だ。当曲はそもそも1963年の長編アニメ映画「わんぱく王子の大蛇退治」のサウンドトラックの編曲ものであり、その第3楽章であるアメノウズメの舞は、ほぼアニメのシーンの音楽そのままなのが特徴で、アニメでもほぼ3分半セリフも無くまるでミュージカル映画がごとく踊りと音楽のみの画期的なシーンとなっている。
児童鑑賞用アニメなので残念ながらもとい当然ながらアメノウズメのポロリやチラリは無いわけだが、曲はエキゾチックかつダイナミズにあふれて、躍動する古代の息吹を感じさせる。これは名曲だ。
3曲目がちょっと地味でしかも単独音源がいまのところ無いのだが黛敏郎が作曲したオペラ「古事記」に天岩戸のシーンがあって、天宇受賣命の舞う音楽がつけられている。
最近はオペラの演出も例えばリヒャルト・シュトラウスのサロメの七つのヴェールの踊りにおいて本当にプロのダンサーが七枚のヴェールを1枚ずつ脱いで素っ裸になるアヴァンギャルドなものもあるようだが、古事記の1996年のドイツにおける初演と2011年の日本での再演では、特に着物が脱げるシーンは無く普通に踊っていた。
これも3分ほどで、後半にはもう天照や思金神のセリフというか歌がかぶってくる。音源は無いが初演のこの部分のシーンが放送されている当時の「題名の無い音楽会」が YouTube にあるので、興味のある方は捜してみるとよいだろう。「黛敏郎:オペラ「古事記」第2幕より」というタイトルで上がっている。(2017年執筆現在)
日本で再演されたものはBSプレミアムで放送されたので、録画したものをもっておられる方もいるだろう。
おそらく3/8+3/8+2/8拍子のオスティナートによるエキゾチックな音楽で、手拍子も入る。現代バレエのような踊りがメインになっており、あまり楽しげな宴会というシーンではないように感じられるが、これも重要なバッカナールシーンと位置づけたい。
3.ストラヴィーンスキィとの共通性
現代においても20世紀音楽界最大の革命といわれるセンセーショナルなバレエ音楽「春の祭典」をもって伊福部をして作曲家になろうと決意せしめたイーゴリ・フョードロヴィチ・ストラヴィーンスキィの創作性は「カメレオン作曲家」などと揶揄されるほど、実はその音楽の多彩さは例を見ないほど抜きんでている。それは大きく分けて、
・ドビュッシーやグラズノーフの影響の残る最初期作品
・三大バレエと原始主義
・新古典主義
・無調と12音主義
の、4つの時期を聴くことができる。
このなかで、最も数が多く時期も長いのは、新古典主義作品だ。つまり、単に作品数でいうと、ストラヴィーンスキィは新古典主義の作曲家となる。
だが、あまりストラヴィーンスキィの新古典主義作品を愛好する人は多くないように感じる。そこまでくればかなりマニアックだ。けっこう各地のオーケストラの定期演奏会や三大バレエの併録でこれら新古典主義作品は演奏され、録音されているが、あまり耳に残っていないと思う。
伊福部にあっては、晩年時代の弟子の言を参考とするに「ストラヴィーンスキィは好きな作曲家だが、三大バレエ以外はどうもねえ」などとゼミナールで云っていたというが、これもまた「伊福部昭 古稀記念交響コンサート 1984」(NOOI-5011〜13)の対談において、興味深い内容が開示された。
それによると、少なくとも70歳当時の伊福部にとって、ストラヴィーンスキィの中で最も好きな作品はピアノとオーケストラのためのカプリッチョであると告白した。
「は?」
ここでも、周囲の古弟子たちはこんな反応。そして私も。
これを読んでいる方で、ストラヴィーンスキィのピアノとオーケストラのためのカプリッチョと云われて「ああ、あの曲ね!」と、曲の冒頭でもフレーズを口ずさめる人が、どれだけいるだろうか。
ストラヴィーンスキィは意外と協奏曲を多作しており、けして通常の概念や編制ではないのが彼らしいところで、8曲もある。作曲年代順に羅列してみたい。
・ピアノと管楽器のための協奏曲(1924/1950)
・ピアノとオーケストラのためのカプリッチョ(1929/1949)
・ヴァイオリン協奏曲(1931)
・2台のピアノのための協奏曲(1931/1935)
・協奏曲変ホ調「ダンバートン・オークス」(1938)
・エボニー協奏曲(1945)
・絃楽のための協奏曲(バーゼル協奏曲)」(1946)
・ピアノとオーケストラのためのムーヴメンツ(1959)
最初の作品ピアノと管楽器のための協奏曲は、ストラヴィーンスキィが「絃楽器の叙情性を排する」とかひねくれた事を云っていた時代のもので、伴奏がほぼ2管オーケストラの管楽器のみの吹奏楽伴奏によるピアノ協奏曲という実に珍しいもの。しかも、その作風は既に完全な新古典主義で、かなりハイドンやモーツァルトの時代のそれに近づいているが、ハルサイみたいなゲロゲロの不協和音が容赦なく混じるし展開も現代風にスリリング。3楽章制で演奏時間は25分ほどの曲。同時代の作品である管楽器のシンフォニーズのエコーもほんの少し聴こえてくる。
次が、伊福部が愛し「こんな作品を書きたい」と自らの創作の目標にまで掲げていたというピアノとオーケストラのためのカプリッチョである。冒頭はストラヴィーンスキィの3楽章の交響曲という作品とそっくりだが3楽章の交響曲がどんな曲か分からない人には通じない。
3楽章制、演奏時間は20分ほどの古典的作品で、対談では松村禎三が少しぼそっと「つまんないですよ……」とつぶやき、伊福部が「ええ!?」と少しムッとしたように反問するや、ハッキリと「全然つまんない曲ですよぉ!(少し震え声)」と師に対して反抗した。周囲では芥川也寸志やらの苦笑も如実に伝わってくるほどだ。
伊福部は「誰に云っても信じてもらえないけどね」などと、とぼけている。
この曲の何が伊福部に「ストラヴィーンスキィの作品の中で一番好きだ」「自分もこういう作品を書きたい」と云わしめているのか……これは考察の余地がある。ピアノソロ部は、特段の斬新さは無いように聴こえる。むしろ伴奏が面白い。ストラヴィーンスキィらしい皮肉っぽさや、ときおり吹き出してしまいそうな変な音形が平気で入ってくる。しかもよく聴こえない。意識して伴奏に耳を傾けないと分からない。そういう部分に、通好みの面白さがあるのかもしれない。ストラヴィーンスキィは、三大バレエでは前面に押し出した斬新さをこういう曲では後ろに隠してしまっている。気付く人だけ気付けばいい、というように。そういう通好みの渋い作風を、伊福部は規範としたいと思ったのだろうか。
また伊福部の「日本を伝統を背負った古典主義」発言とからめると、伊福部はこの曲にストラヴィーンスキィの「ロシアの伝統を背負った古典主義」を聴き取ったのかもしれない。私にはまったくそんな要素は聴こえないけども、スコアをよく研究すると分かるのかも……?
ヴァイオリン協奏曲は4楽章制で30分ほどの、まぎれもなくストラヴィーンスキィの新古典主義時代の傑作のひとつ。これでストラヴィーンスキィは「叙情的ではないヴァイオリンの使い方」をマスターしたのだという。何を云っているのかよく分からないが……本人は、そう思っていたのだ。ここでは、確かにヴァイオリンはガリガリと素っ気なく旋律を奏で、逆にその旋律が古典的に優雅なものなので対比が面白い。
2台のピアノのための協奏曲は、ストラヴィーンスキィ聴きを自認する方でもかなりマニアックな曲として認識していることと推察する。なにせ録音が少ない。4楽章制で30分ほどの、この編制にしては規模の大きな曲に感じる。協奏曲とあるが、実際はピアノ連弾曲なのでジャンルをピアノ曲として扱っている解説書もある。音楽の内容としては合奏協奏曲といえる。ピアノソロに伴奏というものではなく、2台のピアノが延々とからみあう様式を持っている。
協奏曲変ホ調「ダンバートン・オークス」は、これも合奏協奏曲で、編制は室内オーケストラ。3楽章制15分ほどの曲で、地味を究める。副題は委嘱者の住所にちなむ。これも録音は少ない。伊福部と無理にからめるとしたら、ほとんど1管編制なので土俗的三連画に音色が近いが、これはもっとガッシリとした構造の、バッハやハイドン的な造りになっている。古典的な外観を有しつつ、諧謔的な調子やものすごく少し混じるラグライムテイストが実にストラヴィーンスキィっぽい。終楽章のたたみかける執拗さは迫力がある。
エボニー協奏曲も珍しい。これはクラリネット協奏曲だが、編制はソロクラリネットとジャズバンド。3楽章制で10分ほど。エボニーとは、クラリネットの材料である黒檀に由来する。ジャズバンドと云っても、独奏クラリネット、テナーサックス2
、アルトサックス2、バリトンサックス、バスクラリネット2 、ファゴット2 、ホルン、トランペット5、トロンボーン3
、ピアノ、ハープ、ギター、コントラバス、タムタム、シンバル、大太鼓と、ほぼ室内オーケストラに近い特殊ビッグバンド。兵士の物語に通じるラグタイム感を感じる。またクラリネット協奏曲とはいえ、独奏クラリネットはバンドの中でちょっと目立つといった程度のもの。従ってこれも合奏協奏曲といえる。音楽の内容としては正式なジャズではなく、ジャズのイディオムを扱った純粋なクラシック作品。
絃楽のための協奏曲(バーゼル協奏曲)も合奏協奏曲で、絃楽合奏。3楽章制で10分ほど。通称の「バーゼル協奏曲」とは、パウル・ザッヒャーの委嘱によりバーゼル室内管絃楽団の創立20周年記念作品のために書かれたため。ストラヴィーンスキィの協奏曲の中では最もロココっぽい曲調や構成を持つが、ギャリギャリした和声や妙に捩じれた不気味な旋律のカラミなどが、ああ、ストラヴィーンスキィだなあと感じる。
最後がピアノとオーケストラのためのムーヴメンツという、単一楽章で10分ほどの曲。単一楽章といっても細かく5つの部分に別れており、アタッカで演奏される。これが完全に12音技術作品で、ストラヴィーンスキィ77歳、自らの作風の大革新を遂げた記念すべき作品。どのような曲かというと、12音の曲、としか云いようが無いのが文才の無さを露呈し12音曲を文藝的に表現する難しさを如実に感じるところだが、12音技法は作曲に際して厳格なルールが存在し、そのルールを逸脱すると技法的に失敗とみなされる。従って、単なる聴き手にはなかなか判別が難しく、どれを聴いてもみな同じような作品が並ぶ。その中で個性を出すのは至難だ。新ヴィーン楽派が凄いのは、表現確立者にして既に絶対的な個性を持っているところといえる。
その中でストラヴィーンスキィの凄いところは、技法・書法的に何をどういう風にしているのかはまるで分からないが、12音技術でもまぎれもなくストラヴィーンスキィの作風を残していることだ。それはやはり、オーケストレーションを含めた「書法」なのだと思う。ただ、このムーヴメンツより合唱付のレクィエム・カンティクルスなどの、晩年の宗教曲諸作品のほうが個性は強い。またバレエ音楽「アゴン」も12音技法によっており、ストラヴィーンスキィらしい響きが楽しめる。ムーヴメンツでは、まだ手さぐり感が残る。
このように、ストラヴィーンスキィの協奏曲は、ピアノが3曲、ヴァイオリンが1曲、事実上も含めて合奏協奏曲が4曲となっている。
前置きが長くなってしまったが、ここでは、伊福部が作曲家となる契機の曲となったバレエ音楽「春の祭典」の作曲家であり、かつ伊福部へ「自分もこんな作品を書きたいと願っている」と云わしめたピアノとオーケストラのためのカプリッチョの作曲家であるストラヴィーンスキィと伊福部昭の、偶然性も含めた共通点をさぐってゆく。
第1節で既に述べてあるが、まずなんといっても春の祭典と日本狂詩曲の共通性は聴くだけでわかる。これは伊福部の確信犯だと思う。影響されているといっても、ソックリな曲というわけではない。が、そのリズムを強調したコンセプトや打楽器の効果、管絃打を等価値で扱う色彩的なオーケストレーション、土俗的な素材をエスプリの利いたフランス的な書法でまとめた手法など、ストラヴィーンスキィへの憧れが素直によく現れていると思う。
次はストラヴィーンスキィのヴァイオリン協奏曲にほんの一瞬だけ、あまりその曲調にはそぐわないトランペットのフレーズが現れる。「ぱーらら〜らら、らーらら〜」というもので、そう、土俗的三連画3楽章に出てくるフレーズとソックリで笑える。これはしかし、ゴジラのテーマがラヴェルのピアノ協奏曲に「そっくり」という意味での偶然の一致だろう。むしろ、このフレーズをストラヴィーンスキィはどこから持ってきたのかのほうが気になる。まるでストラヴィーンスキィらしくない。なにか、ロシアの民謡の一節なのかもしれない。
また、この非叙情的なヴァイオリンの用法は、伊福部のヴァイオリンと管絃楽のための協奏風狂詩曲に通じる。そしてこれも偶然かもしくは引用したのか分からないが、ストラヴィーンスキィのヴァイオリン協奏曲の第3楽章後半、演奏時間では開始3分ほどのアリアをソロヴァイオリンが奏でている場面で伴奏が小さく「ズンズン、チャチャ、ズンズン、チャチャ」という音形を演奏している。これが伊福部の協奏風狂詩曲の第1楽章最後半、カデンツァからコーダに入った瞬間に、ほぼストラヴィーンスキィの倍のテンポで伴奏が「ズンズンチャチャ、ズンズンチャチャ」という音形をやる。一瞬だが……実に似ている。
次は編制の共通点の一例を。ストラヴィーンスキィの新古典主義作品の傑作のひとつに詩篇交響曲という宗教曲がある。1930年に、ボストン交響楽団創立50周年記念で委嘱されたもの。響きが不気味なので苦手な人もいるようだが、私はこれがことのほか好きだ。茫洋とした音調がシナイ半島に沈む夕日すら想起させ、亡霊の歌めいたラテン語の聖書がなんとも古代的かつ非現実的で原始キリスト教的な良い味を出している。特徴的なのはその編制で、ほぼ5管の巨大オーケストラと混成四部合唱からヴァイオリンとヴィオラ、クラリネットを欠いている。ストラヴィーンスキィによるとそれらの楽器は人間の声の音域や声質に非常に近いので、合唱を際立たせるために排除したのだそうだ。
伊福部には同じように3管オーケストラと混成四部合唱のための合唱頌詞「オホーツクの海」がある。しかも詩篇交響曲と同じようにヴァイオリンとヴィオラを欠いている。クラリネットは知らない。しかし、伊福部はクラリネットが嫌いだったそうなので、聴いていてもあまり目立ってはいない。
これなどは、ストラヴィーンスキィ研究の一環で同様の手法をとったと考えるのが自然だろう。つまり、合唱を際立たせるためにオーケストラから同じ音域、同じ音質の楽器を取り除いてしまったのだ。
また旋律の面では、詩篇交響曲の第2楽章の前奏部分の木管によるフガート主題の冒頭部分が大魔神の木管やコンボオルガンによるテーマの一部とよく似ている。
ちなみに、弟子の方から教えてもらった伊福部昭が明確に嫌いだと名言したという楽器は、以下の通り。
・シンバル、ドラ、トライアングルなとの金属系打楽器……理由:品がよくない。ただし特撮などの映画音楽は「効果音」として重用。
・鍵盤打楽器……理由:理由はよく分からないが、マリンバの低音だけ好き。
・クラリネット……理由:いかにも西洋的な音がする。
・三味線と尺八……理由:若いときのお座敷遊びを思い出して純音にはダメ。鬢多々良の作曲に当たっては、この二つを除くのが条件だったという。
・チェロ……理由:音が甘くなるから。
※好き嫌いを超えた、必然的用法は当然ある。
オペラ=オラトリオ「オイディプス王」という合唱とオーケストラと語り手のための作品がストラヴィーンスキィにあるが、これの到る場所に伊福部が得意としているティンパニや低音の三連符……デンデンデン・デンデンデンの連打が出てくる。おそらく、使っている音(音程)もほとんど同じだと思う。古代ギリシャという題材的にも共通しているためか、雰囲気が伊福部のバレエ音楽「サロメ」によく似ており、サロメもまたそのティンパニと低音のデンデンデン・デンデンデンがよく出てくる。もしかしたら、伊福部が意識してやったのかもしれない。
伊福部の高名な怪獣大戦争と宇宙大戦争のマーチ(アレグロ)の主テーマ。またはゴジラのフリゲートマーチでもあるドレミファミーソーレーソー〜のあのテーマである。本誌主催のオリエント氏の項にもくわしいが、私は、これは元ネタというほどではなく偶然なのだろうと思うが、ストラヴィーンスキィのパストラールという1分半ほどの小品のテーマに実によく似ているのは、けっこう高名だと思う。パストラールはソプラノとピアノを原曲として、ヴァイオリンとピアノ等、いくつかの編制がある。この主テーマがぬるい伊福部マーチというほどで、半音進行でどんどん類似性は離れて行くが、共通性として話題にする価値はあるだろう。
ストラヴィーンスキィのバレエ音楽「オルフェウス」は、同じく新古典時代のバレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」と共にギリシャ神話を題材にしたバレエだ。オルフェウスはアポローンの息子で、竪琴の名手。したがって、バレエではハープが重要な役割を演ずる。冒頭よりハープが単音で、ポン、ポン、ポン、ポン……と音階を下がってくる。……タプカーラの2楽章じゃん! ついでに地球防衛軍じゃん! と、伊福部聴きならすぐに分かる部分だ。これも、元ネタとか参考ではなく、偶然の一致ではあるだろうが、話のネタにはなると思う。
怪獣大戦争や大魔神逆襲のテーマ中の「ボバボ、バー〜ン」という4音はペトリューシュカの第3場「ムーア人の部屋」のコーラングレの不気味でうらぶれたテーマの後のワンフレーズ「ボバボ、バー〜ン」の4音と劇似であり、これは和声も含めて関連性があるかもしれない。
関連といえばペトリューシュカにおいて幕間を太鼓のトレモロでつなぐ手法は、そのまま日本の太鼓にも採用されている。
またペトリューシュカつながりでもう一つ、第2幕「ペトリューシュカの部屋」のフルートのフレーズが、日本の太鼓の第2幕「女鹿かくしの踊り」のオーボエやフルートによる冒頭フレーズによく似ている(調違い)ので確認してみてほしい。
具体に似たような音形があるストラヴィーンスキィと伊福部の関連曲は、私の知る限りこんなものだが、他にも探せばあるかもしれない。伊福部は三大バレエは勿論のこと「三大バレエ以外はどうもねえ」などと云っておきながら、やはりなんだかんだとストラヴィーンスキィの新古典時代の作品に精通していたと思う。かなりスコアを研究していたのだろう。実際「伊福部昭公式ホームページ−暫定版−」にある、伊福部がストラヴィーンスキィ没後、音楽之友ストラヴィーンスキィ追悼号へ寄せた文では、初期の作風から新古典主義への変貌について「同一の感性の両面にすぎなくけっして無節操な変貌だとは思ってない」とし、否定していない。
これら、伊福部とストラヴィーンスキィの共通性はテーマごとにまとめると演奏会や録音、ラジオ放送の面白い企画に使えると思う。いや、編制がまちまちなので、演奏会や録音ではお金がかかる。ラジオ放送や昔でいうレコード鑑賞会などで企画できると思う。
まずやはりパストラールと怪獣大戦争又は宇宙大戦争よりアレグロを比べてもらいたい。小曲なので聴きやすい。伊福部では勇ましいドレミファミーソーレーソー〜のテーマが、不気味にうらぶれて亡霊のように半音進行で漂うストラヴィーンスキィの幽玄的面白さ。
次はなんといっても合唱頌詞「オホーツクの海」と詩篇交響曲だ。この2曲を比べるのは実に意義深い。演奏会でもこれは迫力があって実に効果的なプログラムだと思うのだが、編制が特殊なので資金面で厳しいだろうか。またレコード鑑賞にしても合唱頌詞「オホーツクの海」はLPでしか一般販売は無く、CD化はキングレコードの伊福部昭ボックスの特典でしか無い。なんとかならないものか!
火の鳥とプロメテの火を並べるのも面白いだろう。共にバレエ音楽で「火」つながりでもある。火の鳥は2管編制の1919年版が演奏時間的にも20分でやはり良い。全曲版と1911年版は4管編制で演奏会ではコスト的に厳しいし、全曲版は演奏時間も長い。また1911年版はどういうわけかラストが終曲ではなくカシチューイの踊りで馴染みがない。1945年版も珍しくて良いが、演奏時間が30分とやや長い。
プロメテの火は当然組曲版になるだろうが、作者が正式な組曲を残していないので企画者でオリジナル組曲を考えなくてはならない。私が考えるのは「プレリュード〜プロロゲット〜アイオの踊り〜火の歓喜〜終曲」である。火の歓喜がどうしてもメインになる。これで8分あるので、けっこう難しい。私の選んだ5曲で約20分ほど。火の鳥1919年版も約20分なので、合わせるとちょうど良いだろう。火の鳥の1945年版を使うのであればプロメテの火に間奏曲をどれか加えてもいい。間奏曲は4曲ある。
また、互いに室内楽の極み、洒脱の極み、軽妙の極みとして組曲「兵士の物語」と土俗的三連画は外せない。兵士の物語が七重奏なのに比べて土俗的三連画は演奏者がちょうど倍の14人というのも面白い。演奏時間は逆に組曲「兵士の物語」で25分ほど、土俗的三連画で12分ほどというのも興味深い。楽器の特性をフル活用し、現代的な和声と新古典的な書法にも共通項があるだろう。
ストラヴィーンスキィのヴァイオリン協奏曲と伊福部のヴァイオリンと管絃楽のための協奏風狂詩曲も、ぜひ聴き比べていただきたい。アプローチはまるで異なりながら、どこか通じている部分がたくさんあるのが分かると思う。叙情的であるはずの旋律をわざと素っ気なくガリガリと演奏するソロヴァイオリン。伴奏はどこか土俗的でありつつ、第三者的な視点から達観的に離れて観ている感じ。ゆえに、曲全体がたいへんに醒めた音調になっている。それがカッコイイ。ソロと伴奏が渾然一体となって華やかな音楽空間を演出する通常の概念のヴァイオリン協奏曲とはどこか異なる装いである。楽章も、ストラヴィーンスキィは4楽章制、伊福部は2楽章制。もっとも伊福部は厳密には協奏曲ではなく、協奏曲のような狂詩曲であるため、あまりソロヴァイオリンが活躍しない。が、そこも味だ。
ピアノ協奏曲も比べてみたい。だがストラヴィーンスキィの例の伊福部が大好きだったというカプリッチョと比較して楽しめる伊福部の曲は、ちょっと難しい。ピアノ協奏曲という観点では、伊福部には協奏風交響曲とリトミカ・オスティナータの2曲がある。だが、どちらも規模や楽想からはカプリッチョとは比較しえない。あえてやるならその古典的性格から協奏風交響曲のほうが面白いかもしれない。
むしろ2台のピアノのための協奏曲と、同じく2台のピアノを使い、その使い方もちょっと似ている伊福部のフィリピンに贈る祝典序曲のほうが聴き比べると面白いかもしれない。音楽としては全く異なるが、ピアニズム的には似ている気がする。ピアノと管楽器のための協奏曲とムーヴメンツは比較対象が無い。
交響曲はどうだろう。
ストラヴィーンスキィの交響曲は5曲ある。以下、完成年順に記す。
・交響曲変ホ調(1907/1913)
・管楽器のシンフォニーズ(1920/1947)
・詩編交響曲(1930)
・交響曲ハ調(1940)
・3楽章の交響曲(1945)
この中で、いわゆる純粋な交響曲は初期の変ホ調と、中期新古典主義のハ調のみだ。
交響曲第1番とも記される変ホ調は、2番といえるハ調が2番と記されている例を見ないので、私としては1番とするのに違和感がある。4楽章制で演奏時間は約30分。これがストラヴィーンスキィかよ、というほど古典的で、これだけ聴いたら無名作曲家の習作だが、ストラヴィーンスキィの若書きという観点で聴くと師リームスキィ=コールサコフやチィコーフスキィ、グラズノーフ、その他タネーエフやボロヂーンなどのロシアの先輩作曲家の影響を学ぶことができるだろう。
フランス時代に作曲された管楽器のシンフォニーズは1楽章制で13分ほどの管楽合奏曲であり、通常の概念の交響曲ではない。管楽器のための交響曲というタイトルが通例だが、直訳すると「のための」ではなく「の」であり、かつ複数形である。交響曲の複数形を知らないので、そのままシンフォニーズとする。解説によると「連続する響きあうものの集合体」という意味があるらしく、交響曲としてしまうと語弊があると感じる。そのため交響曲に含めない場合もあるが、せっかくなのでここでは含めた。
詩編交響曲は既に述べてあるが、3楽章制で演奏時間25分程度の特殊編成カンタータ。これも合唱曲として分類される場合もあるが、合唱交響曲であり、私はこれこそ交響曲に含めなくてはならないと思う。また、既に合唱頌詩「オホーツクの海」と比較している。
交響曲ハ調は、新古典主義時代の名曲。4楽章制で30分ほど。ハ調なので響きが明るいが、この時期ストラヴィーンスキィは家族を次々に失い、戦争の影響もあって住み慣れたパリ、そしてスイスを離れてアメリカへ亡命した苦難の時代だった。本人は「音楽は感情を反映しない」などと云ってあえて無機質に明るさを装っているが、それが逆に不気味だ。楽想的には特筆するようなものは聴こえにくいが、ハルサイばりの過激さやうらぶれた感じが古典的な外枠の中にギュウギュウに押しこまれ、いまにも爆裂せんばかりの緊張感が素晴らしいし凄まじい。
3楽章の交響曲は、実質的にはハープとピアノのための二重協奏曲で、演奏時間は25分ほど。3楽章制。元々の発想が管絃楽のための協奏曲だったとのことで、その性格が色濃く残っている。けっきょく交響曲になったので、ハープやピアノのソロは協奏曲ほど目立たない。逆に、作曲しているうちに目立たなくなったので結果として交響曲にしたのかもしれない。楽想的には地味なので「失敗作」扱いする評もあるが、戦争末期の世界的な混乱期にあってストラヴィーンスキィ自身の混迷や混乱、動揺を聴き取ることができるだろう。
では伊福部と比較する。
伊福部の交響曲は協奏風交響曲とタプカーラ交響曲の2曲のみ。交響譚詩や交響頌偈「釈迦」は含めない。
単純に比較すると3楽章の交響曲とタプカーラということになるだろうが、両者は共に3楽章制というだけで特段の接点はなく、響きや音調、曲調、楽想としても、聴き比べても大して面白くないと感じる。ここはいっそ協奏風交響曲と3楽章の交響曲を比べると面白いかもしれない。共に「協奏風交響曲」なので。片や協奏曲に近く、片や合奏協奏曲に近いという構造も、比べるとその独奏の扱いの違いが面白いだろう。
そうなるとタプカーラと比較しえるのは、むしろ交響曲ハ調だろう。音調的にタプカーラを純粋に新古典主義とするのは、せめてそこはロマン派寄りの国民楽派だろうという意味で無理があるかもしれないが、伊福部本人としてはそう思って作曲したのだろうし、じっさい国民楽派を代表するドヴォジャークの6、7、8番交響曲は完全にブラームスの影響下にあり国民楽派寄りの新古典主義といったほうが良いくらいなので、タプカーラもそれと同列に考えると、むしろ交響譚詩の延長上で国民楽派寄りの新古典主義と云える。交響曲ハ調のほうが外観はいかにも古典的だが、曲想はタプカーラのほうが古典的だろう。交響曲ハ調はハルサイよりリズムが複雑な部分もあり、しかも聴いていてよく分からないという「斬新さ」だ。その互いの逆転現象を楽しめる。
閑話休題3 〜三大バレエのロシア語タイトルについて〜
ロシア語タイトルと云っても私はロシア語の専門ではないので厳密には間違いもあるだろうことを含めおき頂きつつ、調べた範囲でなかなか興味深いのでここに記す。
ストラヴィーンスキィの三大バレエは、初演がフランスなので正式な原タイトルはフランス語だと思われる。フランス語では
L'Oiseau de feu(ロワゾ ドゥ フュウ)
Ptrouchka
Le sacre du printemps(ラ サクレ ドゥ プランタン)
となる。輸入CDでよくある英語タイトル
The Firebird
Petrushka
The rite of spring
は、フランス語からの英訳だと思う。
それで、ロシア語のタイトルはどうなのかというと、ちょっと面白い。というのも、ストラヴィーンスキィはもちろんロシア人なので、フランス語からの訳ではなく、ロシア語タイトルはロシア語で最初から考えていたと考えられる。ロシア語ではそれぞれ、
Жар- птица(ジャール プチーツァ)
Петрушка(ペトリューシュカ)
Весна священная(ヴェスナー スヴィシェーンナヤ)
となる。
火の鳥はロシア語で直訳すると「灼熱の鳥」になる。こっちのほうがちょっとカッコイイ。バレエのための造語ではなく、ロシア民話で元ネタの1つ「イヴァン王子と火の鳥と灰色狼」からきている。
ペトリューシュカは固有名詞なので何語でも「ペトリューシュカ」なのだが、ピエロのことを指すと同時にロシアの男性名の「ピョートル」の愛称形でもある。ロシア名は何種類も愛称形があって、年上格上からの愛称形、同輩からの愛称形、年下からの愛称形等々が厳密に決まっており、間違えると失礼に当たる。日本でも先輩を愛称で呼ぶのに「〜ちゃん」と呼んだら失礼だろう。「ペトリューシュカ」は年下格下への愛称の一種。
ちなみにピョートルは英語名でピーターのことであり、プロコーフィエフの高名な「ピーターと狼」は「ピョートルと狼」のことであり、さらに厳密に云うとピョートルの愛称形の1つ「ペーチャと狼」がロシア語原タイトルとなる。
さて春の祭典だが、日本語のこれは英語からの意訳だと感じている。「rite」は儀式、祭式、儀礼ということで、祭典というお祭り全体のイメージより本来は生贄の儀式の狭義の意味での「祀り」「神事」のほうが近いと思う。フランス語の「sacre 」はもっと狭義で、捧げられる儀式、神聖な儀礼、神聖な、という意味であり「神聖な春」「春の奉献」という意味になる。
ロシア語もやはりフランス語と同じで、直訳で「神聖な春」となるのが興味深い。священная は「神聖な」という意味の священный(スヴィシェーンヌィ)の格変化。祭典は祭典でも、フェスティヴァル的な単なるお祭りではなく、もっと土俗的で、かつその神聖さを強調した聖なる生贄の儀式であるところの「春の神事」というのが、原題のニュアンスに近いと感じられる。
おわりに
伊福部とストラヴィーンスキィに関して好き放題な読み物を書いたが、単なる思いこみに端を発しており、学術的な検証はまったくなされていないのでその点はご承知おき願いたい。これは論文ではない。伊福部とストラヴィーンスキの聴き方の楽しみの一端を、遊びとしてご提示しただけである。少しでも御共感いただけるところがあれば幸いに思う。
前のページ
後の祭