さかゐまに
2022夏コミックマーケット100へ出品したオリエント工房主催同人誌「伊福部ファン」第4号へ寄稿したものを全文掲載します。ウェブで読みやすいよう、改行は1行空けにしてあります。
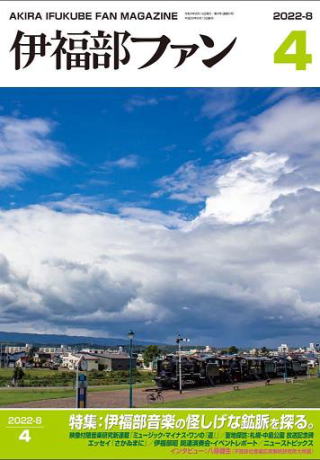

さかゐまに
2022夏コミックマーケット100へ出品したオリエント工房主催同人誌「伊福部ファン」第4号へ寄稿したものを全文掲載します。ウェブで読みやすいよう、改行は1行空けにしてあります。
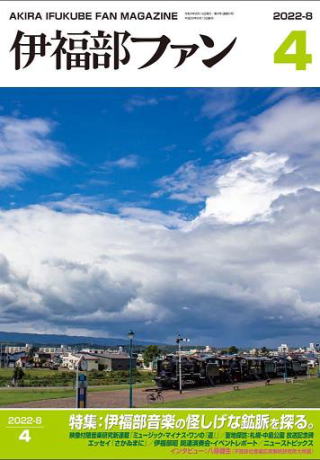

1. まぼろしの曲
令和に入り、コロナ禍にあっても伊福部の演奏会が引きも切らず、ますます注目が集まっているところである。また、プロのオーケストラの定期演奏会に、にわかに伊福部が取り上げられてきた感もある。
企画演奏会ではなく定期演奏会に取り上げられるというのは、クラシックの楽曲のステータスにおいてやはり段違いの物がある。
そんな伊福部において、何種類もCDが出ているメジャー曲もあれば、音源になっていない、あるいは音源が激レアCD/LPとなっている「幻の曲」もある。
サウンドトラックは別にして、純音楽や機会音楽では、例えば『管絃楽司伴“鞆の音”』はCDが関係者のみ配布の限定非売品であるし、『合唱頌詩“オホーツクの海”』は音源がLP とBOX セットの特典CDしかない。
しかし、CDは比較的入手容易ながら、録音がその一種類しかない曲もある。これも、ある意味「幻の曲」と言ってよいと考える。
なぜなら、おそらく一般的な伊福部ファンのほとんどの方が「滅多に聴かない」あるいは「聴いたことがない」と答えると思うからである。
それは『因幡万葉の歌五首』だ。
伊福部ファン御承知の通り、伊福部家は古代律令時代より因幡国宇部神社の宮司を代々務めていた。
明治になり、時の政府の方針もあって伊福部家は宮司を辞することになり、昭の父、伊福部利三が一家を引き連れて北海道へ渡った。
平成6年(1994年)、鳥取県国府町(当時)に因幡万葉歴史館が開設されるにあたり、その記念として縁のある伊福部へ新曲が委嘱され、同年10月30日に初演された。
奈良時代の天平宝字2年(758年)に因幡守に任ぜられ、因幡国国司を務めた大歌人・大伴家持の歌四首(万葉集)と、家持の叔母で妻の母である大伴坂上郎女の歌一首(古今和歌六帖)からなる演奏時間20分ほどの歌曲で、編成はソプラノ、アルトフルート、二十五絃筝という、日本人作曲家の手による他の歌曲を見渡しても、この作品以前にも、令和4年(2022年)7月執筆現在この作品の後にも例のない、実に伊福部らしいものとなっている。まさに、歌曲といえば伴奏がほぼピアノしかない世界に対する挑戦とも言える。
思えば、伊福部は既にソプラノとティンパニという特異な編成を世に送りだしていた。その挑戦の精神が、ここに結実している。
伊福部最晩年の仕事の一つであり、作品表を見てもこの後に完成したオリジナル作品は『二十五絃箏曲“琵琶行〜白居易ノ興ニ效フ”』(1999)と歌曲『蒼鷺』(2000)しかなく、ほかは編曲作品のみだ。
前号にとりあげた『琵琶行』の稿でも触れたが、この『因幡万葉の歌五首』を「愛聴している」伊福部ファンが、どれほどいるだろうか。音楽鑑賞は自由であり、聴きたいものだけを聴けばよいのは当然で、聴きたくないものを無理に聴く必要は無い。
だが、未知の隙間を埋める知的好奇心の探求は、マンネリ化した耳と脳に爽やかで新鮮な刺激を与えてくれる。
さて、本稿の執筆開始は令和元年であり、本来であれば前号の第3号で発表する予定だった。が、思うところあって急遽本号である第4号用に準備していた『琵琶行』と差し替えた。
元号「令和」は万葉集から採られたことで話題となったが、令和にちなみ、私も当曲を取り上げてみたいと思った。その後に『琵琶行』を取り上げるに至り、この両曲は題材からして伊福部の中でも際立って珍しいのではないかと感じはじめ、非常に関心を持つようになった。
なぜならば、伊福部の先祖が大伴家持と同時代に宮廷に仕えていたという歴史や、伊福部家の家学が老子であり漢学に精通していたことにも関わらず、コンサート作品にあってそれらを直接的に表した楽曲は、それぞれ『因幡万葉の歌五首』と『琵琶行』しか無いからである。
これは、結果として非常に面白い特徴だと思う。
なお、楽譜の表紙には単に『因幡万葉の歌』とあるが、かつて然る伊福部門下の方に伺った所によると、伊福部がタイトルの後に「五首」と入れたほうがよいですね……と話していたというので、ここでは『因幡万葉の歌五首』とする。
2. 因幡万葉の歌五首(言の葉)
まず、歌詞に採用されている和歌を確認したい。
○第1曲(大伴家持:万葉集 第20巻4516)
新しき 年の初めの 初春の 今日降る雪の いや重け吉事
あらたしき としのはじめの はつはるの きょうふるゆきの いやしけよごと
新 年乃始乃 波都波流能 家布敷流由伎能 伊夜之家餘其騰
天平宝字3年(759年)正月、前年に因幡国の国司に任じられた家持が郡司(地方責任者)や郡司配下の地方役人を国府へ招待し、宴会を開いた時の一首。
新年元旦の歌として今日も高名であり、全20巻ある万葉集の最後を飾る歌である。
当時は、新年に雪が降ることは吉事だったそうで、意味は「新しい年を迎え、今日降っている雪のように、良いことがたくさん重なりますように!」というほどのもの。
万葉集最後の歌が、歌曲の第1曲となっているのも面白い。
祝い歌なので、因幡万葉歴史館開設を祝う意味もあったと推測される。
歌曲集の最初から、純粋に荘厳かつ爽やかで清々しい気分にさせてくれる。
ちなみに「あたらしき」ではなく「あらたしき」である。
室町時代ほどまで、新しいは「あらたしい」と読んでいたそうで、なぜ「あたらしい」になったのかは諸説あるというが、現代でも、その読みは「新たに」に受け継がれている。
なお、初めて聴いていたときは、ずっと「あたらしい」に空耳していた。歌詞(和歌)を確認しても、「あたらしい」に空目していた。思いこみというのは、恐ろしいものである。
○第2曲(大伴家持:万葉集 第19巻4290)
春の野に 霞たなびき うら悲し この夕影に 鶯鳴くも
はるののに かすみたなびき うらがなし このゆうかげに うぐいすなくも
春野尓 霞多奈毘伎 宇良悲 許能暮影尓 鶯奈久母
天平勝宝5年(753年)、因幡へ来る前の時代、赴任先の越中から都へ戻っていた家持が旧暦の2月23日に、ふと興が乗って詠んだとのこと。
情景的には大したものではなく、そのままだ。春霞がたなびいている夕暮れに、ウグイスの声を聴いての一首である。
しかし、意味はなかなか深そうだ。
「春の野原にうっすらと霞がたなびいている夕暮れにホーホケキョを聴いて、なんとも悲しくなっちゃったなあ」というほどのものだが、自分には、この歌は情景ではなく心情を鑑賞すると感じられる。
また、このとき家持はこれのほかにも一首、すなわち同時に二首詠んでいるばかりでなく、二日後にもう一首、計三首詠んでいる。
同時に詠んだ歌(第19巻4291)がこちら。
わが屋戸の いささ群竹 吹く風の 音のかそけき この夕べかも
わがやどの いささむらたけ ふくかぜの おとのかそけき このゆうべかも
和我屋度能 伊佐左村竹 布久風能 於等能可蘇氣伎 許能由布敝可母
これは、「自分の家の僅かな竹やぶに、微かに風がそよいでいる音が聞こえる夕べだねえ」などという程度の意味であるが、これもまた情景的には大したことはなく、なんとも侘しい、もの悲しい感じが伝わってくる悲観的な心情を味わうものと考える。
そして二日後の2月25日に詠んだ歌(第19巻4292)がこちら。
うらうらに 照れる春日に 雲雀上がり 情悲しも 一人し思えば
うらうらに てれるはるひに ひばりあがり なさけかなしも ひとりしおもえば
宇良宇良尓 照流春日尓 比婆理安我里 情悲毛 比登里志於母倍婆
これなどは、「麗らかなぽかぽかした春の日射しにヒバリが飛んでおり、一人物思いにふけっていると悲しくなってきちゃったよ〜」くらいのものだが、普通、春というと冬が終わって心がウキウキ弾んでくると思われるが、家持はどうしたわけか春に悲しくなってしょうがないのである。春なのに……。
現代であれば、卒業だの別れだので春にセンチメンタルになる心情や情景もあるだろうが、天平の昔に、家持はいったいどうしてしまったのだろうか。
これらは連作と考えるべきという解説もあり、密接にリンクして家持の複雑な心情を表していると観てよいだろう。
とにかく家持はこの時、相当にナーバスだったようで、春霞が棚引く夕べにウグイスを聴いて悲しくなり、同時に家の庭の小さな竹藪をそよ風が通る音を聞いてもの悲しく歌に詠み、二日後には暖かい春の陽気にヒバリがピーチクパーチク飛んでいるのを見て悲しくなっている。理由が判然としないが、とにかく春に悲しくてしょうがないのだ。
思うに、家持の時代には、古代豪族の名門大伴氏は、没落というほどではないが新興勢力の藤原氏にすっかりお株を奪われてしまい、中央の要職を外されて地方と都を行ったり来たりしている。
当時の意識高い系の都人にとって、地方の閑職に「飛ばされる」というのは、前号の白居易と同じく、現代に生きる我々には想像もつかないような衝撃と沈鬱を与えていた。
その憂さを晴らすためには、歌でも詠むしかなかったのかもしれない。
○第3曲(大友家持:万葉集 第19巻4139)
春の苑 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つ娘子
はるのその くれないにおう もものはな したてるみちに いでたつおとめ
春苑 紅尓保布 桃花 下照道尓 出立◇嬬 ◇=女偏に感
第2曲とうって変わって、まさに春のウキウキ感がストレートに伝わってくる歌。と言っても、第2曲も慟哭の響く悲歌というわけではなく、センチメンタルでナイーヴな心情を前面に出しているように感じるもの。
それと比較して、こちらは非常に明るい情景的な歌となっている。
天平勝宝2年(750年)3月1日、家持の越中赴任時の歌。
特に深い意味はなく、北陸の遅い春に桃や李の花園を鑑賞しての一首。
「春の庭の、赤く匂い立つような桃の花に照らされた道に、美少女が立っとった!」という他愛もないものだが、この時、家持は同時に二首作っている。
もう一首(第19巻4140)がこちら。
吾が園の 李の花か 庭に降る はだれのいまだ 残りたるかも
わがそのの すもものはなか にわにふる はだれのいまだ のこりたるかも
吾園之 李花可 庭尓落 波太礼能未 遺在可母
「はだれ」とは、うっすらと降る春雪のこと。
つまりこの歌は、「庭を真っ白におおうのは李の花か、それとも春雪がまだうっすらと残っているのか」といったほどのもので、先の歌に比べるとしっとりして落ち着いており、大人の雰囲気だ。さすがに先の歌だけだと、はしゃぎ過ぎたと思ったのかもしれないし、この歌があって対比することで先の歌の純粋にハッピーな感じや春の爽やかな萌ゆる美が際立つ。
また「春の苑…」は、とても漢詩的な雰囲気を出しているのも見逃せない。
三国志の桃園の誓いではないが、桃園というのは実に中華的なメタファーである。
国風文化の花咲く平安時代に比べ、奈良時代はまだまだ唐の影響が大きく、万葉集にも唐文学の影響があるという。
平安時代には、漢詩はおよそ宮廷に仕える者の必須教養だったし、和歌の世界でも、何かしら漢詩にかけるのは面白みに通じ、教養のアピールにもなっていた。
この歌にそういう意図があるのかどうかは分からないが、ただ単に桃の美少女萌え〜! なだけではなく、漢詩的、異国情緒的な雰囲気を醸して面白みを出しているとも感じとれる。
そうなると、出で立つ美少女は桃園に見えた幻影なのかもしれない。
○第4曲(大友家持:万葉集 第19巻4181)
さ夜ふけて 暁月に 影見えて 鳴くほととぎす 聞けばなつかし
さよふけて あかときつきに かげみえて なくほととぎす きけばなつかし
左夜深而 暁月尓 影所見而 鳴霍公鳥 聞者夏借
天平勝宝2年(750年)4月の歌とある。「明け方の月の下で、影が浮かんでいるのが見える。ホトトギスが鳴いており、心惹かれますなあ」というほどのもの。
越中赴任時代なので、懐かしがっているのは奈良の都のことであるという解説もあるが、ここでの「なつかし」は懐かしいではなく、面白い、楽しい、興味が尽きない、心が惹かれるという意味となる。古語辞典を引いても、一般的に「なつかし」は、心が惹かれる、親しみを覚える、愛おしいという意味である。
これは現代語でいうところの「犬が懐く」の「懐く」の形容詞にあたる言葉で、懐古の意味の「懐かしい」は、もっと後(一説には鎌倉時代)にできた言葉だという。
また、前後の歌を鑑みても、「なつかし」は非常に興味深い、心が惹かれるという意味のほうが合っている。
なんにせよ、実に詩情豊かな歌だ。
ただの月ではなく、暁月……すなわち明け方近くの、東の空が白んできて薄墨をまいたような暁闇のころ、天の片隅にまだ残る半ば白い月というのも趣深い。
また、ホトトギスは夜に鳴くことでも知られ、この歌でも明け方の月の影に聞こえている。
おそらく、山影か何かの奥から聞こえてくるのだろう。
家持は、徹夜で暁を迎えたのだろうか。
暁闇のほんの短い時の中で、暁月と周囲の風景の影と声だけ聴こえるホトトギスに、面白さ、興味深さを感じ、なんとも心惹かれている。
この時代から明治の俳壇にまで、ホトトギスという鳥はおよそ文学の象徴ような鳥だ。鳴き声はかなり鋭く響き、印象に残る。暁の月とホトトギスで、興味や郷愁を誘う妙も味わいたい。
さて、この歌もまた、他に二首(第19巻4182、4183)詠まれている。
また、短歌に先立ち長歌(第19巻4180)が詠まれている。
万葉集は、けして短歌集ではないことが分かる。
題詞(前置き)として、「ホトトギスの声を鑑賞していると実に飽きないので、思いをこめて歌(長歌)一首と合わせて短歌を作った」とある。
その長歌がこちら。
春過ぎて 夏来向へば あしひきの 山呼び響め さ夜中に 鳴く霍公鳥 初声を 聞けばなつかし あやめぐさ 花橘を 貫き交へ かづらくまでに 里響め 鳴き渡れどもなほし偲はゆ
はるすぎて なつきむかへば あしひきの やまよびとよめ さよなかに なくほととぎす はつこゑを きけばなつかし あやめぐさ はなたちばなを ぬきまじへ かづらくまでに さととよめ なきわたれども なほししのはゆ
春過而 夏来向者 足桧木乃 山呼等余米 左夜中尓 鳴霍公鳥 始音乎 聞婆奈都可之 菖蒲 花橘 乎貫交 可頭良久麻泥尓 里響 喧渡礼騰母 尚之努波由
短歌は一般に馴染みがあるが、長歌は専門に嗜んでいないと、なかなか馴染みがないものと推察する。
まるで神主の祝詞みたいだが、長歌があっての短歌である。
「春が過ぎて夏になり、山一帯に響くように、夜中じゅうホトトギスが鳴いている。その初鳴きを聞くと、興味が尽きないんだなあ。菖蒲(あやめ)や橘の花を髪飾りにする五月まで里中に響くように鳴いているが、ずっと愛でていられるね!」
およそこのような内容であり、家持はどんだけホトトギスが好きなんだよ、という思いしかない。
そして、長歌への反歌として、短歌三首が来る。
一首めが「さ夜ふけて…」であり、続く二首がこちら。
霍公鳥 聞けども飽かず 網捕りに 捕りてなつけな 離れず鳴くがね
ほととぎす きけどもあかず あみとりに とりてなつけな かれずなくがね
霍公鳥 雖聞不足 網取尓 獲而奈都氣奈 可礼受鳴金
─
霍公鳥 飼ひ通せらば 今年経て 来向ふ夏は まづ鳴きなむを
ほととぎす かひとほせらば ことしへて きむかふなつは まづなきなむを
霍公鳥 飼通良婆 今年經而 来向夏波 麻豆将喧乎
鳴くまで待とうホトトギスではないが、いよいよ家持のホトトギス推しが尋常ではなくなっている。
「さ夜ふけて…」ではまだ詩情があったが、「ホトトギスは聴いても聴いても飽きないから、いっそ網で捕まえて懐かせれば、常に鳴いてくれるんじゃね?」からの「そのホトトギスをずっと飼い続ければ、来年の夏になったら、真っ先に鳴いてくれるんじゃね?」になると、もはやただの偏執狂的なコレクター願望だ。
またそうなると一首目の情景は、徹夜で仕事でもしていたおり、明け方近くにふと聴こえてきたホトトギスの鳴き声に気づいて外を見やると、白い暁月に映る影の向こうから聴こえていた。耳を澄ましていると癒され、心惹かれて一首詠んだ……という情景的なものではなく、実は単に一晩中デュフデュフと笑いながらひたすらホトトギスを聴いていて、気がついたら夜が明けかけており、ふと外を見やって、いやはや暁闇に響きわたるホトトギスもまたいいですなあ! などと詠んだのではないか……とすら思えてくる。
もはや、重篤のホトトギスオタクという他は無い。
○第5曲(大伴坂上郎女:古今和歌六帖 第四帖)
わがせこが 面影山の さかゐまに 我のみ恋ひて 見ぬはねたしも
わがせこが おもかげやまの さかいまに われのみこいて みぬはねたしも
万葉集は資料や参考サイトも多いのだが、古今和歌六帖はちょっとマニアックだ。
万葉の時代の歌に間違いはないのだが、古今和歌六帖の編纂が平安時代とのことで、万葉仮名の原文は不明。
作者の大伴坂上郎女は「おおともの さかのうえの いらつめ」と読むが名前ではなく、住んでいた場所(坂の上)にちなむあだ名のようなもの。
名前は、伝わっていない。
家持の父、旅人の妹で、家持の叔母にあたるだけではなく妻の母でもある。
面影山は因幡国府より見える三つの山(因幡三山)のひとつで、それほど高い山ではないが、象徴として歌に詠まれている。
因幡国府から良く見え、奈良の藤原京から見えた天香久山(あまのかぐやま)に似ていたことから、因幡に赴任してきた国司達が奈良の都を思い出すというので面影山と呼ぶようになったという。
「さかゐま」とは、何のことだかよく分からないらしい。
「(私は)面影山の麓にいる貴方の面影を恋慕っており、見ることができないのはメッチャ悔しいです!」というほどのものである。
面影と面影山をかけているのが分かる。
「わがせこ」はそもそも夫や恋人を指すというのだが、ここでは当然、家持のことであろう。
「ねたし」は「悔しい、癪に障る、忌ま忌ましい」という意味で、それに詠嘆の「も」がついている。
「自分ばっかり(一方的に)家持を恋い慕っているのは、メチャクチャ悔しい!」というのだ。
なぜ悔しいのかというと、自分だけが……という想い(あるいは、自分だけがそうなっている境遇)になるだろう。
その中には、いつも家持といっしょにいることができる自分の娘(家持の妻)への嫉妬もあるかもしれない。
恋愛感情とは限らないのかもしれないが、当時奈良と鳥取などというのは、二度と会えないかもしれないというほどの距離であることは想像に難(かた)くなく、家持の小さいころから面倒を見てきたとされる郎女の……古代人の情愛の深さが偲ばれる。
その後、家持は出世して無事に奈良の都に戻ってきた。
そのような、因幡ゆかりの思慕の歌で当曲は締められる。
改めて思うに、天平勝宝8年(756年)頃にかの正倉院ができているくらいだから、本当に大昔である。
令和4年(2022年)現在、1260年以上も前になる。
そのときに作られた歌(詩)が現代に伝わって、単なる研究対象ではなく、一般に鑑賞され愛好されているということが、恐ろしくすらある。正倉院の御物も奇跡だが、万葉集も奇跡と言えるだろう。
まして、当時の語句がほぼそのまま日本語として通用する。
その奇跡の古代語へ、現代の音楽をつけることの意義。
そして面白さ。
それも伊福部が作曲した事実に感嘆し驚嘆する。
アイヌや北方諸民族の言語へ曲をつけたものや、現代詩へ作曲したものはあれど、委嘱とはいえ万葉集というのは意外だった。
3. 因幡万葉の歌五首(音曲)
続いて、楽曲としての5曲を俯瞰する。
作曲に関して、伊福部は『日本海新聞』1994年11月3日号掲載の記事で、以下のとおり答えている。
「依頼されたのが二年前、出来上がったのがほんの直前ですから、かなり苦労しました。一時はオープンに間に合うのかどうか、心配したほどです。
作曲に当たってはまず、『新しき年の始の…』を雅楽ふうに仕立て、『春の野に霞たなびき…』で因幡の野原を想像しました。
もっとも、『春の野に…』は因幡でうたった歌ではないのですが…。
次いで、『春の苑紅にほふ…』で乙女の浮き浮きした気持ちを出し、さらに『さ夜ふけて暁月を…』で、家持の持ち味の自然への思いを表現しようと試みました。
そして、最後は大伴坂上郎女の『わが兄子が面影山のさかいまにわれのみ恋ひて見ぬはねたしも』を置くことで、人の情念に迫ろうとしました。
家持は以前から好きで、いつか機会があったら作曲したいと考えていましたが、読めば読むほど、風格というか、気品みたいもの(原文ママ)があって難しい。
それを傷付けないようにしながら、因幡の地の雰囲気を出すように努めました。
音楽的に言うと、箏(こと)が少しずつ遅れて出るカノン技法を使いました」
「小学生のころ、アイヌ村が近くにあったことから、日本の成り立ちというか、歴史に関心を持つようになりました。
やがて、日本人は日本の歌を書かないとだめだ?と思うようになり、現在に至っているわけです。
万葉集や大伴家持には以前から関心を持っており、特に家持なんか、普段から読んでいました。
格調が高く、雄渾(こん)な感じがあって、日本の文学として相当レベルが高いのではないか、と思ってきました。
これはあくまで想像なのですが、家持が因幡の国守だった時代、私の祖先なんかも付き合っていたではないか。
そう思うと、とても身近な存在に思えますね」
「家持の気品と因幡の雰囲気込め「 因幡万葉の歌」作曲者、伊福部昭氏に聞く」『日本海新聞』1994年11月3日より
ここで伊福部は「家持は以前から好きで、いつか機会があったら作曲したいと考えていました」と、語っている。
十代後半の最初期の歌曲に『平安朝の秋に寄する三つの詩』なるものが存在しており、若いころから日本の古典文学に興味があったと推察され、この言葉に嘘は無いと思われる。
また「万葉集や大伴家持には以前から関心を持っており、特に家持なんか、普段から読んでいました。」とも語っている。
伊福部と言えば家学が老子であり、日本の古典文学、雅楽的なもの、雅びなるものに憧れたのはむしろ盟友の早坂文雄で、伊福部はあまりそういうものに興味を持っていなかったというイメージが強かったが、民族的・北方的なものへの強い共感と興味と同列に、日本の古典的な世界への共感と興味も当然ながらあったのだろう。
なぜなら、万葉や雅びの世界とて、日本民族的な世界に変わりは無いのだから。
○第1曲
「新しき 年の初めの 初春の 今日降る雪の いや重け吉事」
アダージョ・グラーヴェ(重々しいアダージョ)から、歌曲集は始まる。「雅楽ふうに仕立て」とあるが、序奏からいきなり和楽そして正月っぽい。
それは、もちろん狙っているのだと思うが、お屠蘇でも飲んで浮かれているという感じはしない。
小節線(拍子)無しのアルトフルートによる無限旋律のような序奏は、武満の遺作『フルートのための“エア”』をも連想させ、日本的な無常観を強く表す。
なお、このアルトフルートには Flute, without tonguing, like Japanese style と指示書きがある。
日本の横笛類に(調べた限り、特別に製作されたものを除き)基本的にアルトの音域のものは無い。
ここの指示は具体的な楽器を示すのではなく、単純に日本の笛みたいに吹け、というものだろう。
日本の横笛類は用途に応じて種類が別れており、代表的なものでは主に雅楽に使われる龍笛と高麗笛、雅楽や神楽に使われる神楽笛、能で使われる能管、歌舞伎や民謡、村祭等で吹かれる篠笛がある。
お祭でピーヒャラピーヒャラと吹かれているのは、篠笛である。
篠笛だけ長さによって音域が別れているが、最も大きい一本調子と呼ばれるものでも、ノーマルなフルートより短い。
その他、大陸より伝来した明清楽器の中に、明笛(清笛)という横笛がある。
これも何種類かあるが、大きさ(長さ)的に、篠笛と音域はあまり変わらないと判断できる。
では、なぜ伊福部はアルトフルートという「アルトの音域の横笛」を選んだのだろうか。
横笛ではなく縦笛の一種である尺八ならば、大きさによってはアルトの音を吹けるものもある。
また、音色・音調的にも、どうもこのアルトフルートは横笛類ではなく、尺八をイメージしているように聴こえる。
であれば、同じアルトの音域でもアルトサックスやアルトクラリネット、ましてヴィオラではなく、尺八に音色の近いアルトフルートを選択した理由も理解できる。
ところが、だ。
私が以前、前述の然る伊福部門下の方に伺った所によると、伊福部は邦楽器の中では尺八と三味線を嫌っていた、というのだ。
邦楽器合奏曲の傑作『郢曲“ 鬢多々良”』委嘱の際も、尺八と三味線を除いて良いのなら……と条件をつけたという。
事実『鬢多々良』に、尺八と三味線は使用されていない。
理由は他愛のないもので、特に三味線は若い時のお座敷遊びを思い出すので、純然たるコンサート音楽には相応しくないように感じられる……という、非常に個人的な心情に由来するものだったという。
そのため、like Shakuhachi style としなかったのではないか。
さて、その無常的かつ日本的な序奏に続く箏の登場から6/4拍子となり、拍子木のようにリズムが次第に速くなる、いかにも日本的な律動が聴こえてくる。
まさに新年を祝う古式に則った儀式のような、重厚な気配がする。
序奏が変奏で繰り返され、小経過部を経て4/4拍子にて「新しき…」と歌唱がはじまる。
日本語の音節に合わせたのだろう、合間に5/4拍子も挟まって、堂々として重々しい。
「初春の…」から音が一気に上がり「今日…」で頂点となって「降る…」で、一気に下がる。
大きな山を作り、聴くものを集中させるうえ、音の下降によって雪が降っている情景すら感じさせる。
そこから箏が3/4拍子でリズミカルに踊って場の雰囲気を変え、最後の部分「いや重け吉事」が歌われる。
この箏は、まるでしんしんと降りつもる雪の描写のようだ。
短い3/4拍子と2/4拍子を繰り返す間奏の後、また3/4拍子で「今日降る雪の…」からリフレイン。
ここは、1回目に歌われたときより拍子と音が絶妙に異なる演出になっている。
序奏が短く変化し、後奏として戻ってくる。
箏が先程のリズミカルな音型の断片を奏でながら、一曲目を終える。
厳粛な祝い歌らしい格調の高さに、身を正すような気分となる。
実際の祝宴や古の人が歌った際にはもっと寛いだ雰囲気だったろうが、ここではそんな古代へ想いを馳せて、あくまで品格や格式を優先し、万葉の世界を自由に楽しんでいる。
○第2曲
「春の野に 霞たなびき うら悲し この夕影に 鶯鳴くも」
続いて、第2曲はレント・ラメントーゾ(悲しそうなレント)と指示がある。
伊福部としては「因幡の野原を想像し」たというが、短歌の内容に合わせたラメントーゾ(悲しそうな)という発想記号がキモだろう。
侘しげな箏の単音からはじまる序奏は、冒頭から3/4、4/4、5/4と拍子が複雑に入れ変わる伊福部リズムで、主旋律を模すフレーズも実にしっとりとした、まさに美しくも「うら悲し」い情感を演出する。
「春の野に…」と入ってくる歌唱も、同じく3拍子4拍子5拍子、はては6拍子まで加わって進むが、聴いている分には長音が多く、よく分からないように構成されている。伊福部は変拍子ありきでそのような音楽を書いているのではなく、伊福部の思い浮かぶ旋律を記譜したら変拍子になっただけなのだ。
箏をメインの伴奏にして、長く歌われる主旋律の、なんという寂しさ、もの悲しさか。「春の野に…」どころではなく、シューベルトの歌曲集『冬の旅』も真っ青の寒さである。
「うら悲し…」が終わると、アルトフルートがこれもまた無常観たっぷりに入ってくる。
春風どころか、まるで枯れススキの揺れる晩秋の風のようだ。
「鶯鳴くも」でいったん終わり、マーラーの交響曲『大地の歌』の第6楽章を彷彿とさせる、アルトフルートの美しくも寒々しい短い間奏が現れる。
音が低いので、まるでフクロウの鳴き声のようだが、その実、音型としては「ホーーーホケキョ」と、ウグイスの鳴き声にも聴こえてくる。
もしそうだとしたら、まるでメシアンだ。
しかも、ご丁寧に箏がザワザワと風の音を模す。
そんな情景を経て、「この夕影に…」からリフレイン。
またも、ウグイスが侘しく鳴く。
同様に、なんとも侘しく、まさに心寂しい秋の野のような雰囲気で短い終結部を奏して、ポツン、と終わる。
「鶯鳴くも」も、まるで「泣くも」と云った寒さ。
情緒的でありつつ、ペシミズムの極致を聴くような枯れきった響きに、恐怖すら感じさせる。
曲想としても、かなり悲歌的な雰囲気だが、しかし慟哭というわけではない。
あくまで、静謐に悲しみを歌う。
ウグイスの鳴く、ほがらかな春の野に、孤独な悲しみを。
歴史館開館のお祝いの場で初演されるにあたり、どういう理由でこの悲しく、かつ寂しい歌が選ばれ、このような悲しさを強調した曲調・音調となっているのか、理由が知りたい不思議な一曲だ。
○第3曲
「春の苑 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つ娘子」
第3曲は、モデラート・パストラーレ(田園のようなモデラート)である。
前曲と一転して、恋のように心踊るまさに春の音調。
5曲中で唯一、モデラートの歩くようなテンポであり、ここを中心に曲はレントとアダージョに挟まれている構造となる。
中心にして要の楽章であり、まさに曲全体がマーラー流のシンメトリー構造になっている。
伊福部としては「乙女の浮き浮きした気持ちを出し」たそうなので、これはまさにその通りの、素直な音調となっている。
しかしその中にも、細かい藝が詰まっている。
アルトフルートと箏で、旋律のワンフレーズ全てを使用する長い前奏の後、ほぼ同じ旋律で「春の苑…」から歌われる。
「紅におふ 桃の花…」のところの「紅に…」と聴こえるような、ひっかけフレーズも面白い。
音がリズミカルに上下して、じつに朗らかで暖かい、花見の酒宴でほろ酔い加減となったような良い気分となる。
さらに面白いのは、中間句である「桃の花…」がレーファーラーソーレーと下降系のフレーズにより下のレで終わるのに対し、終結句である「出で立つ乙女」の「乙女」が、ラーラーラーとまるで中間部か途中経過のような終わり方をすることである。
これは「北海道讃歌」の最後「ほーっかーいどー」を、ラの1つ上の実音のシでシーシー・シシーと終わるのを彷彿とさせる、伊福部独特の終結感だ。
どこかふわっとした印象を聴く者へ与え、終結であるが永遠に広がって続いて行くような、広大な大地か大海原を見るような解放感を与えてくれる。
この歌であれば、まさに視界一面にどこまでも広がる花吹雪の舞う桃園の情景だろうか。
さらに、
・春の苑(冒頭フレーズ)
・紅におふ桃の花(終結っぽい感じ)
・下照る道に(冒頭フレーズに近似)
・出で立つ乙女(途中経過っぽい感じ)
これが、伴奏を微妙に変えて2回ずつ(2回目は、アルトフルートのカノン構造が面白い)計4回繰り返されるので、非常に幻想的、幻惑的かつ蠱惑的な効果を聴く者へ与える。この乙女が、桃園の幻影であることを意識しているようにも聴こえてくる。
なお、当曲の主旋律は、伊福部の担当した映画など数々の伊福部作品で聴かれる高名なものである。
私は、同じ伊福部ファンでもサントラ系は門外なので、詳しい方にご教授いただいたところ、少なくとも映画「殺したのは誰だ」「暗黒街の顔役」「ちいさこべ」「婦系図」「奥只見ダム 第二部」「帝銀事件 死刑囚」に旋律が流用されているという。
その他にも、フィンランド民謡『野いちご』にとても「良く似ている」のは、注目に値する。『野いちご』は日本語訳され、唱歌としてYouTube で聴くことができるので、聴き比べると楽しいだろう。
ちなみに、ショスタコーヴィチによる『ソプラノ、テノール、室内オーケストラのための歌曲「フィンランドの主題による組曲」』(1939)(『7つのフィンランド民謡組曲』、単に『フィンランド組曲』とも)にも、この『野いちご』(直訳すると『イチゴは実る、赤い実に』)が採用されており、同旋律のショスタコーヴィチによる斬新な編曲を楽しむことができる。
伊福部と関連があるような、無いような、であるが……。
ここは「他人の空似」ということにしておきたい。
また、ショスタコーヴィチのこの「秘曲」は、演奏記録のみで楽譜は行方不明だったものを、2000年に楽譜が発見されたことを付け加える。
フィンランド語の歌唱はテンポが速く、発音の関係もあってかリズムも微妙に違って、唱歌に比べてあまり伊福部節とは似ていない。
○第4曲
「さ夜ふけて 暁月に 影見えて 鳴くほととぎす 聞けばなつかし」
アダージョ・カルマート、ノットゥルノ(夜想曲、穏やかなアダージョ)とある。
ここで、夜想曲が登場する。しかも、アダージョだ。
5曲中、最も謎めいているのは、この第4曲ではないだろうか。
というのも、前段にある通り、この歌での家持の心情は、大好きなホトトギスを聴いて「なつかし」、すなわちウキウキでデュフデュフなのである。夜想曲どころか、第3曲を超えるお祭気分のアレグロでもいいくらいだ。
伊福部によると「家持の持ち味の自然への思いを表現しようと試みました。」とのことだが、「自然への思い」が自然讃歌のような壮大にして重厚な気分ならまだしも、重度のホトトギス推しでは、ちょっと内向的で軽い印象だ。
しかも「家持の持ち味」とある。家持の歌を専門に勉強したわけではないので、その全てを把握しているわけではないが、この『因幡万葉の歌五首』にある四首だけを観ても、確かに家持は身の回りの自然に対し、鋭敏な感性を持っている。
だが、現代と奈良時代では、周囲の環境がまったく異なる。
当時は、奈良の都以外では、周囲はもう「自然だらけ」というか、「自然しかない」と言っても過言ではない。
いや、現代のような「文明」の反対語としての「自然」という概念すら無いと思う。
あくまで「自然への思い」は、現代人の我々から観て、家持の感性を現代的に解釈しているにすぎない。
歌の旋律を模す箏による序奏は、琵琶かギターを彷彿とさせる音調で、3拍子4拍子6拍子が混じる。
アルトフルートは、ホトトギスどころかフクロウの声のように響く。まさに、夜曲の様相を呈する。
そこからおもむろに「さ夜ふけて…」と歌われるが、『合唱頌詩“オホーツクの海”』や『ゴジラ』の「帝都の惨状」、『ビルマの竪琴』の「白骨街道」等の、伊福部ファンお馴染みの「伊福部レクイエム」とも言える例のあの旋律を髣髴とさせる音調である。
しかも、それを裏付けるかのように、トリステッツァ(悲しそうに)と指示がある。
伴奏の箏は、一転してリズムを支え、軽やかに演奏される。
そこに、冷え冷えと白い月が輝いている。「暁月に…」で音がドーンと上がって、聴いている者の視点も上がる。
暁闇に影を濃く残す、天空に白く光る残月を見上げる。
そして「影見えて…」で音と共に視線がゆっくりと下がって来て、まだ黒々と残る影を見やる。次第に伴奏の箏が小さくなり、やがて消える。
そこから「鳴くほととぎす…」と歌われるが、むしろ異様な静けさが身に沁みる。「聞けばなつかし」では、心情を掻きむしる一瞬の箏の乱舞。
再び箏のリズミックな伴奏が間奏となって登場し、執拗なこのオスティナートは、一晩中鳴き渡るホトトギスの象徴なのではないかと思えてくる。
そしてアルトフルートが、冒頭のフクロウの主題とも云えるフレーズを短く奏で、少し変奏された「鳴くほととぎす…」からリフレイン。
しかし、二度目は葛藤の箏が大人しい。
「聞けばなつかし」で歌唱が終わり、後奏で箏がホトトギスの主題とも云えるフレーズを続けるが、それは次第に明け方の影の向こうへ消えてゆく。
長歌短歌を合わせたホトトギス推しの歌四首の内、「さ夜ふけて…」だけを見ると、暁闇にしみじみとホトトギスの声を聞いていた家持が、越中から遠く奈良の都を思い出して悲しい気持ちになっているようにも解釈できるが、それだと古語の意味及び伊福部の言葉と矛盾する。
すなわち「なつかし」は懐かしいではなく心惹かれるという意味であるし、伊福部は家持の「自然への思いを表現しようと」した。
この「自然への思い」とは何なのかというと……ホトトギスへの、偏執狂的かつ異常なほどの愛好である。
その強烈にして苛烈な執着は、ホトトギスを捕まえて飼い馴らしてしまえばいいという、監禁ストーカー系の愛にまで発展している。
その独占欲と無邪気さを音楽にしたならば、「いやあ、ホトトギスって、本当にいいものですね!」という(ちょっと歪な)幸福感に溢れた音調になってもおかしくないと思うのだ。
が、この漆黒の闇に潜む殺意のような冷たさ、美しさと悲しさは、どこから生まれたのか、非常に不思議なのである。
まさに『因幡万葉の歌五首』最大のミステリーだ。
あくまで想像だが、ホトトギスには夜に鳴き続けて冥府に誘っているとされる事や、中国の望帝杜宇による故事(古代蜀の王であった杜宇は死後ホトトギスとなり、古蜀が滅亡した際に嘆き悲しんで吐血するまで鳴いたという)から「死のイメージ」もあるといい、中国の古典に精通していた伊福部は、ホトトギスというと杜宇の嘆き悲しむイメージが強くあって、それを重ね合わせたのかもしれない。
○第5曲
「わがせこが 面影山の さかゐまに 我のみ恋ひて 見ぬはねたしも」
これは、レント・ドロローゾ(悲痛なレント)とある。
最後の曲にまで「悲痛な」という指示であり、5曲の内3曲が情景的にも心情的にも悲しい曲調となっているのが非常に興味深く、当曲最大の特徴になっていると感じる。
これも一貫して3拍子4拍子5拍子が複雑に入り交じるが、やはり旋律が自然なのでそれを感じさせない。
まず気づくのは、たっぷりと主旋律を模す序奏のアルトフルートの旋律が、かなり低いこと。バスに近い音域か。
まさに、地下からの囁きだ。箏はアルペッジョ(と、言ってよいのかどうか分からないが、とにかくハープ等で言うところのそれ)を多用し、心の乱れ、ざわめきを表しているかのようだ。
「わがせこが…」で歌唱がはじまるが、それも低い。
地を這うが如く、悲しみが伝わってくる。
いや、これは切なさか。
「さかゐまに…」から、箏が複雑なソロを一小節。
「我のみ恋ひて…」も、朗唱のように響く。
「見ぬはねたしも」を歌った後、箏が悔しさ、忌ま忌ましさを存分に表して、苦しい心の内を示す。
「我のみ恋ひて…」からリフレインするが、ここで音が一段高くなって、ついに恋しい心情が爆発する。
それを箏がさらに狂ったように絃と心を掻きむしって、繰り返される「見ぬはねたしも」から、アルトフルートがその心情を落ちつかせるかのように、朗々と歌によりそう。
そして後奏で箏が想いの丈を天空へ飛ばす。
アルトフルートは、天空を行く風だ。
都から因幡へ向かう、白い魂の鳥だ。
この空の向こうの遥かな土地に、想いの人はいるのである。
古代人の思慕の強さを、かいま見ることができる。伊福部の「人の情念に迫ろうとしました。」という言葉とピッタリと符合する、素晴らしい締めの一曲だろう。
片山杜秀責任編集『文藝別冊 伊福部昭』では、因幡の古代伊福部氏族の支配権を取りあげた大和朝廷より派遣された役人である家持の歌に、かつてその地を治めていた古代豪族の末裔である伊福部が作曲することや、明治初期に政府の方針で職すら奪われ北海道という「超僻地」に追いやられた一家に生まれた伊福部がその因縁の地である鳥取の家持の記念館のために曲を書くということの心情を分析し、精神的和解、皮肉、さらには諦観まで読み取ることができ、「一筋縄では行かない」としている。
まったく同感である。
第4曲のように、和歌の内容というか、歌詞の意味合いと曲風・音調が違いすぎる曲がある。
また、第2曲の哀しみ、第5曲の悔しさのように、そもそもこの歌(歌詞)は開館記念に相応しいのか? という意味で、選歌そのものに疑問が残る部分もある。
曲も、歌の内容の通りに重い。
反面、第1曲・第3曲のように、いかにも開館記念に相応しい歌詞と曲もある。
色々なアプローチから鑑賞することができ、伊福部の数ある歌曲の中でも、本当に「一筋縄では行かない」面白い位置に存在する歌曲だと思う。
4. 因幡万葉の録音壱種
当曲は長く録音が一種類しかなかったが、令和3年(2021年)末に二種類目が世に出た。
……と、思いきや、諸事情により発売早々に回収されたので、あっと言う間に一種類に戻った。
また、令和4年(2022年)7月執筆現在、編曲版や抜粋等でYouTubeに5種類、録音が上がっている。
まず平成21年(2009年)に伊福部家が代々宮司を務めた鳥取の宇部神社本殿において奉納演奏をした際に、アルトフルートの代わりにバリトンが無言歌を歌い、歌唱はテノール、さらに、打楽器や伊福部が研究していた明清楽器である月琴、阮咸(げんかん)を加え、二十五絃の代わりに二面の十三絃と十七絃の箏を使用したものである。
これは演奏に際し編成上の諸事情があったと推察するが、アルトフルートと二十五絃箏という特殊楽器を使用したために、再演の難しさを物語る一例とも言えるだろう。
編曲は田中修一。
是か非かで言うと、個人的にこういう改編(場合によっては改悪)は大いに非となるのだが、マーラーが野外イベントでベートーヴェンの『第九』4楽章の一部を金管アンサンブルに編曲した例を見ても、純然たるコンサートではなくイベント等の特殊な形式・形態での披露では、ケースバイケースの部類に入る場合もあるだろう。
次は、平成27年(2015年)に演奏された、女声合唱と二十五絃箏によるもの。同じく、アルトフルートパートを女声合唱が無言歌で担っている。
歌唱も女声合唱。
また、第3曲に明清楽器である明(清)笛が使用されている。
編曲は甲田潤。
その次が令和元年(2019年)、石川県白山市の聖興寺における「令和元年第245回千代尼忌」というイベントでの演奏。
こちらは、アルトフルートがあるが、二十五絃箏をピアノが担っている。
歌はメゾソプラノ。
これは、編曲無しで直接二十五絃箏パートをピアノで弾いていると思う。
他の演奏と比べ、テンポがちょっと速い。
が、歌曲としては、これくらいが適当な気もする。ただし残念ながら、1曲めと4曲めしかアップされていない。
また、その2曲しか演奏されなかった可能性もある。
次が、ラ・ガッシアというグループによる「悠久の祈り?時を超えて」という令和3年(2021年)の演奏で、第1曲のみ。二十五絃箏にアルト音域の中世フルート、ソプラノの編制だが、仏具の「りん」を音階ごとに多数吊るして叩く打楽器や、中世ヨーロッパの弦楽器が加えられている。
最後に、令和4年(2022年)1月15日に行われた根岸一郎の伊福部昭歌曲集のコンサートの模様が、抜粋でアップされている。
その中に『因幡万葉の歌五首』もあるのだが、アップされているのは第5曲のみ。
根岸一郎のバリトン、金子展寛の二十五絃箏、高本直のアルトフルートによる。
演奏レベルも非常に高い。
これらはライヴ演奏を民生機器で撮影したものが多く、必ずしも音響や画像が良いものではないことを付け加えておく。
原曲としてCD録音は、先述の通り以下の一種類である。
ソプラノ:藍川由美
アルトフルート:中川昌巳
二十五絃箏:野坂惠子(当時)
カメラータ・トウキョウ 30CM-391-2
平成7年(1995年)2月のセッション録音。
初演の翌年……いや、初演から4か月後の録音であり、当時としてはまさに伊福部の最新曲だ。
藍川の情感たっぷりでありつつ、冷静さを持って情感(あるいは感情)に流されない第三者的な傍観を帯びた悲しみや寂しさのバランスの良さは、見事と言うに尽きる。
中川のアルトフルートも凄い。ペシミズムを極めた侘しさが素晴らしい。
それでいて、時に力強さ、瑞々しさも失わず、古代の生命力を現代へ息吹で伝えてくれる。
けして前に出すぎず、しかし主張もしっかりしている。
箏は令和元年(2019年)に亡くなられた野坂である。
伴奏ながら、時に枯淡の粋にまで達し、時に桃園の幻想を見せてくれ、時に月夜の冷え冷えとした空気感から時空の彼方にまで精神を運んでくれる表現の幅広さ、技術の確かさには脱帽する。
ソリストとしても大変高名かつ実力者の二人を伴奏にし、まさに完璧な布陣だ。
その三者三様があって、単純に聴衆として感じるに、この録音は決定盤と言えるものになっている。
むしろ、究極の演奏になってしまっている、と言ってもよいかもしれない。
これを超える……いや、これへ匹敵する演奏は、かなり難しいだろうし、この演奏を超えることができるのは、まさに藍川由美ご本人にしか成し得ないだろう。
とはいえ、一般聴衆の一人としては、作者直伝の奥義を極めた演奏から、縁もゆかりもない野の奏者が単にプログラムの一つとしてただ楽譜の通り演奏する凡庸的演奏まで、種々聴き比べることができると、楽曲としての面白みが深まると思うし、それが独り立ちした「作品」としてのあるべき姿であると思う。
この曲に限らず、伊福部の歌曲は初期三部作である『ギリヤーク族の古き吟誦歌』『サハリン島先住民の三つの揺籃歌』『アイヌの叙事詩に依る対話体牧歌』あるいは『シレトコ半島の漁夫の歌』の録音ばかりで、後期の渋い作品はほとんど録音が無いのは、やはり需要が無いからだと推察する。
聴く方の姿勢が変われば、商品として制作する方の意識も変わるだろう。
が、そこは無理に(義務的に)聴いても作品に失礼だし、真の理解や楽しみとも言えない。難しいが、それが現実でもある。
本稿が、当曲を愛好するファンが少しでも増える一助になれば幸いである。
5. 考察
さて、私が以前、やはり前述の然る伊福部門下の方に伺った所によると、この五首は伊福部が自身で選んだとのこと。
そこで、伊福部が当曲を作曲するにあたり委嘱の経緯等を知るべく、鳥取市にある因幡万葉歴史館に電話及びメールで照会をした。選歌を含めて委嘱したのか、あるいは伊福部の方から選歌を申し出たうえで委嘱を受けたのか、その辺りの事情を知りたかった。
なぜなら、その選歌の経緯が、当曲の鑑賞に重要な意味を持つと考えたからである。
しかし、もともとこの作品は平成4年(1992年)国府町(当時)教育委員会からの委嘱であったのだが、国府町は平成16年(2004年)に鳥取市に編入されて廃止となった。
そのためか、残念ながら当時の文書、資料等は所在が不明であり、また歴史館開設に携わった人にも色々と訪ねてもらったのだが、詳細は不明とのことであった。
お忙しい中、ご対応頂いた因幡万葉歴史館には、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
そのような訳で、伊福部がどうしてこの五首を採用したのか、詳細は不明のままとなった。
しかし、本当に「一筋縄では行かない」ような複雑な心境で、五首のうち二首を悲しみや悔しさを歌ったものにし、一首は「なつかし」な歌詞の内容と相反するような、もの悲しい音調で作曲したのだろうか。
歴史館の開館記念の委嘱に。
某BS 番組の「英雄達の選択」ではないが、伊福部の心の内に分け入ってみたい。
まず、歴史館開設の話が来る。伊福部としては、ふうん……。
という程度だったかもしれない。
なにせ、いくら以前から好きだった家持に関する施設とはいえ、片山の指摘のとおり因幡を支配していた古代豪族である伊福部氏を「討伐」「征服」した側であろう、大和朝廷が設置した役所を記念する歴史館なのだから。
しかし、古代豪族の埋葬文化を知る貴重な発見として国の重要指定文化財にもなっている、伊福吉部臣徳足比売(いふくべの おみ とこたりひめ)の骨蔵器(骨壺)に関連して、歴史館にも徳足比売の常設展が置かれるという。徳足比売は、文武天皇の時世に采女(うねめ)として大和朝廷へ仕えた、伊福部氏の祖先の一人である。
そうなれば、歴史館の開設記念で縁のある伊福部に新曲をと頼まれて、断るわけにもゆかないだろう。
新曲は、主に家持の詠んだ歌を歌詞として作曲をするという委嘱。当初から伊福部に選歌まで委嘱したのか、伊福部のほうから委嘱の条件として選歌を申し出たのか、打ち合わせをしている内に選歌も伊福部が行うこととなったのか、その辺の事情は残念ながら分からなかったが、とにかく、選歌は伊福部が担う。
伊福部は作曲に二年もの歳月をかけ、しかも初演スケジュールギリギリに完成しているとのことだが、まずこの選歌の作業に非常に時間をかけたようである。
じっくりと悩みぬき、選びに選んで、この五首に決定したという事実のみが残っている。
他にどのような候補があったのか、興味はつきないが、結果として選ばれたこの五首を、改めて順に見てゆこう。
ちなみにCD等の解説では、家持の歌である四首は全て因幡で詠まれたものになっているが、正確には第1曲に採用された「あらたしき…」だけが因幡で詠まれ、後は因幡赴任前に越中や奈良の都で詠まれている。
1曲目は、正月の祝い歌。
これは順当だろう。
歴史館開設のお祝いにも相応しい。
2曲目に、さっそく春霞にうら悲しい歌が来る。
しかも、ウグイスの声を聴いて。朗らかなウグイスを聴いて悲しくなるというほどの心境に、伊福部は何を共感し、何を託したのだろうか。
「因幡の野原を想像しました。」と語っているが、そんな単純なものではないだろう。
それだけならば、他にも歌はあるはずで、わざわざ「霞たなびき うら悲し」い歌を用意する理由はなんだろうか?
歴史館竣工のめでたさに、素直に喜べない複雑な心持があったのだろうか。
めでたいもの、喜ばしいものに悲しさを感じてしまう反骨感も出て、伊福部らしいアイロニーと言えるかもしれない。
3曲目は華々しく、明るいもの。
これは第2曲との比較で、3曲目に来るのは順当と考える。
内容としても、桃源への陶酔と、花びらの下に立つ美少女への陶酔、さらには古代への陶酔が混然となって面白い幻想感、蠱惑感を出す。
問題は、残る2曲だろう。
4曲目は、静寂の暁闇に響き渡るホトトギスに面白さを感じ、ウキウキと心惹かれるもの。
しかし、曲調で言えば、ここでは拡大解釈として懐古としての意味も含まれているように感じられる。
しかもただの懐かしさではなく、白居易と同じく、辺境に身を置いて都を懐かしむ、嘆きを含んだもの。
これは、伊福部に合わせると切ない。
伊福部氏が、明治以降の世にあっても日本の超僻地にして超蛮地・北海道より、因幡の都を懐かしんでいると読める。
また、ホトトギスにあるという死のイメージも強いように感じられる。
なんにせよ、歌詞の内容と楽想が真逆に聴こえるという、謎めいた一曲となっている。
そして5曲め。もう、悲しさや寂しさを超えて、「ねたまし」いまでに心情が爆発している!
伊福部は、坂上郎女の悔しさ、忌ま忌ましさに共感していたのだろうか? それとも、坂上郎女の心情にかこつけて、伊福部自身が何かに悔しがり、癪に障っていたのだろうか? そのようなことを軽々しくは言えないが、あえて言うとして、過去の伊福部家の境遇から見て、宇部神社の宮司を追われたことへか? 同時代の現代作曲家が、時代に持て囃されていることに対してか? それとも何か……まったく想像もつかないものに対してだろうか? いや、それとも単純に人間の情念に迫ったこの歌が好きだっただけなのか?
また、けしてメジャーとは言えない「古今和歌六帖」から採用したこの歌は、面影山を歌ったものとして国府町では高名だったようで、他意はなく単にそのために採用したものか? 謎は深まるばかりである。
この曲順も興味深い。曲の順番は、楽曲全体の、組曲としての構成に係わるもので、無視はできない。
オーケストラの組曲ものでも、構成を考えてバレエや映画音楽等の原曲と順番を入れ替えるというのはよくある。
それほど、一つの作品としての「組曲」の構成は重用だ。
単純に明暗で分けると、明暗明暗暗となり、緩急で云うと緩緩急緩緩となる。
明暗だと前半3曲と後半2曲という構成、緩急では第3楽章を中心としたシンメトリー構造として考えることができる。
全体の流れはどうだろう。
祝歌→春の朗らかさの中に悲しみ→桃源に遊び→死の鳥ホトトギスへの執拗な興味→情念を虚空に飛ばす。
飛ばした青空に、それまでの悲しみも悔しさも、全て流してしまう枯淡の境地。
許すというのも烏滸がましく、軽々しい気がするほどの、深い達観の心情。
悠久の時の流れの前には、どのような感情ももはや遠い幻となる。
悔しさと愛情の入り交じった煩悶と、それを流し去る無常に涙を流し、精神的和解を図る。
まさに、人間伊福部による人間讃歌であろう。
そんな聴後感すら、わき起こってくる。
文藝別冊の片山の考察はページ数の関係もあってか、駆け足気味に書いているが、これは旋律や音楽そのものはシンプルを極めた伊福部流ながら、まさに「一筋縄では行かない」複雑な心境を秘めた味わい深い難曲であろう。
また、いざ作曲にとりかかると作曲家というのはその内側の心情とは別に、技術的には冷静となる。
かの、ベルリオーズの『幻想交響曲』が良い例だが、やれ失恋で自殺未遂をした際の阿片で見た幻想だの、猟奇的な幻覚だのが先走りするが、本当に阿片を吸ってポヤーンとしている人間があんな複雑な曲を書けるはずもなく、作曲に際しての根源的な標題とは別の問題で、作曲している最中は当然ながら素面だ。
己の胸中に勃興する複雑な心情を踏まえて、冷静に、伊福部が藍川の歌唱、野坂の筝を前提に何度も協議し、試演し、考察し、映画音楽(ゴジラVSスペースゴジラ)の依頼を断ってすら集中して仕上げた、晩年の意欲作でもある。
伊福部の歌曲リストの中で、北方民族系でもない、更科作品でもない、映画音楽系でもない、ともすれば異様なほどポツンと浮かんで見えるこの『因幡万葉の歌五首』が、深い自らの心境・心情というある種の特殊性を孕んだ、おそらく他に例のないアルトフルートと二十五絃箏という編成的にも意欲作という観点で観ると、俄然、面白みが輝きを放ってくる。
また、第4曲の謎など、我ながら面白い発見があり、歌詞である万葉の世界の面白さも些少ながら勉強できた。
改めて、今のところあまり日の当たらない伊福部作品の一つである『因幡万葉の歌五首』の魅力を味わえたのは収穫だった。
参考
1) 古今和歌六帖輪読会『古今和歌六帖全注釈 第四帖』, お茶の水女子大学附属図書館 l
2) ウェブサイト『讃岐屋一蔵の古典翻訳ブログ』
3) ウェブサイト『たのしい万葉集』
4) ウェブサイト『万葉集ナビ』
5) ウェブサイト『くらすらん』
6) ウェブサイト『詩と音楽』
7) ウェブサイト『Wikisource 万葉集』
8) 「 大伴家持の歌に曲つけた 因幡国守次官の子孫 伊福部昭さん」, 『 読売新聞 鳥取版』, 1994年10月15日, 朝刊.
9) 「 大伴家持の和歌 荘厳に響き渡る 因幡万葉歴史観会館を記念」, 『 山陰中央新報』, 1994年10月31日.
10)「 家持の気品と因幡の雰囲気込め「 因幡万葉の歌」作曲者、伊福部昭氏に聞く」,『 日本海新聞』, 1994年11月3日.
協力
鳥取市因幡万葉歴史館 鎌澤さん
タバスコさん
井戸屋猫八さん
前のページ
後の祭